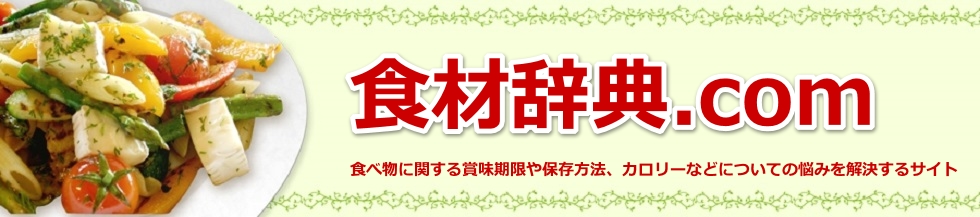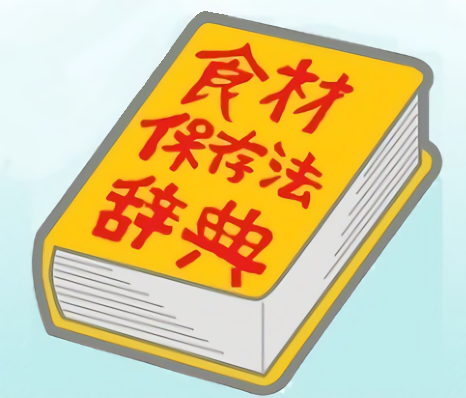���ڂ���̐H�߂��Ŕ������F�ɁH������Ė{���H�K�ʂȂ�֔���P�H

�Â��Ăق����肵�����ڂ���B
�T���_�ɂ��Ă����������A�V�Ղ�ɂ��Ă����������A
�v������P�[�L�ȂǃX�C�[�c�ɂ������B
����Ȃ��ڂ���̗��ɂȂ��Ă�����͑����͂��I
�����ł��B
���ڂ�����Ė�����A������Ƃ��炢�H�߂��Ă��˂��c�H
�҂ҁ[���I���ӂł��B
�����⌒�N�ɗǂ��ƌ����Ă��邩�ڂ���ł����A�H�߂��͂������ċt���ʂɁc�H
�Ƃ����킯�ō���́A���ڂ���̐H�߂��ɂ��e���ƓK���ׂĂ܂Ƃ߂܂����I
���ڂ���̐H�߂��Ŕ������F�ɂȂ銹��ǂɁH
�݂����H�߂��Ĕ������F���Ȃ邱�Ƃ͂悭�����܂����A���ڂ���̐H�߂������l�ɔ������F���Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
����́A�J���`���i�J���e���j�̐ۂ肷���ɂ���Ĉ����N���銹��ǂƌĂ��Ǐ�ł��B
��Ɋ���̂Ђ�A���̗��ȂǂɐF�f�������\�ꉩ�F�������܂����A���ڂ����F���Ȃ��Ă��Ȃ��̂��A���t�Ƃ̈Ⴂ�ł��B
���Ö@�͓��ɂȂ��A�J���`���̐ێ���T����Ύ��R�ƌ��ɖ߂��Ă����̂ň��S���Ă��������ˁB
�܂��A����ǎ��̂͑傫�ȊQ�͂Ȃ��̂ł����A�������ǂ̐l�͊���ǂɂȂ�₷���Ƃ����Ă��܂��B
����́A�J���`�������ɗn���₷�������������Ă��邽�߁A�������ǂ̐l�͌����J���`�����㏸���₷�����߂ł��B
�Ȃ̂ŁA����ǂ̏Ǐo�����́A�������ǂɂȂ��Ă��Ȃ������ӂ��Ă��������ˁB
���ڂ����H�߂���Ƒ���́H
���̓�����YES�Ƃ�NO�Ƃ������܂��B
���ڂ���͈�ނƓ��l������������̂��߁A�_�C�G�b�g���͍T�������������ƌ����Ă��܂��B
�����������@��H�ו��ɂ���Ă̓_�C�G�b�g���̋��������ɂȂ��Ă���܂���B
���ڂ���̑���Ȃ��H�ו��ɂ͂R�̃|�C���g������܂��B
���ڂ���̑I�ѕ�
���ڂ���ɂ͑傫�������ĂQ��ނ̂��ڂ��Ⴊ����܂��B
�e�����ڂ���Œm������{���ڂ���ƁA���т����ڂ����݂₱���ڂ���Œm���鐼�m���ڂ���B
�����͖���H�������łȂ��A�h�{���ɂ��Ⴂ������܂��I
�_�C�G�b�g�ɂ������߂Ȃ̂́A���{���ڂ���ł��B
���m���ڂ���̓����ʂ�100������17g�ɑ��āA���{���ڂ����100g����8.7g�Ɩ�2�{�̍����I�I
�܂����{���ڂ����䥂ł�Ɠ������オ��A���m���ڂ���͋t��䥂ł�Ɠ�����������̂ŁA���{���ڂ���͏Ă��A���m���ڂ���͎ς�A�Ƃ������g���������d�v�ɂȂ�܂��B
�H�ו�
�_�C�G�b�g���ɂ������߂Ȃ̂��A�Y�������i�āA�p���A�˗ނȂǁj�̑���ɂ��ڂ����ێ悷����@�ł��B
��̒��ł͓����̑������ڂ���ł����A���͂��p���ɔ�ׂ�ƒ�J�����[�I
�����ē��������Ȃ��I
�����ĐH���@�ۂ₻�̑��̉h�{���������I
�u�������_�C�G�b�g�ɂ͂҂�����̐H�ނł��B
�����@
���ڂ��Ⴊ�_�C�G�b�g�Ɍ����Ă��邩�ۂ��͒����@���d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
���ڂ���̒�ԂƂ�������V�Ղ��O���^���A�V�`���[�Ȃǂ͌��킸�����ȃ_�C�G�b�g�ɂ͕s�����Ȓ����@�ł��ˁB
�܂��A���ڂ���̓}���l�[�Y����Ƃ̑����������̂ł����J�����[�ɂȂ肪���ł��B
���ڂ�����w���V�[�ɐH�ׂ�ɂ́A�V���v���ɃI���[�u�I�C���Ń\�e�[������A���X�`�ɉ������肷��̂������ł��ˁB
���ڂ���{���̊Ö����y���݂܂��傤�B
���ڂ����H�ׂ�Ƃ��̓K�ʂƉh�{���ʁI

�ł́A1���ɂǂꂮ�炢�̂��ڂ����H�ׂ�Ƃ����̂ł��傤���H
���̐l�̑̎���̊i�ɂ����܂����A���ς��Ă��悻100�`200���Ƃ����Ă��܂��B
��ʓI�Ȃ��ڂ���̎ϕ��̑傫���ł����ƁA3�`5���炢�ł��傤���B
�ӊO�Ə��Ȃ��Ɗ�������������邩������܂���B
�Ö��������A�������₷���̂ŁA������薡����ĐH�ׂĂ݂Ă��������ˁB
�X�ɂ��ڂ���ɂ͔��e�⌒�N�ɂ����������ʂ��I�I
���݂Ă����܂��傤�B
�@�H���@��
�H���@�ۂ𑽂��܂ނ��ڂ���ɂ͕֔�����̌��ʂ����I�I
100g������3g�O��̐H���@�ۂ��܂܂�Ă���̂ŁA1���̕K�v�H���@�ۗ�17g�̂�����1/6���ۂ邱�Ƃ��ł��܂���B
����ɂ��ڂ���ɂ͐��n���H���@�ۂƕs�n���H���@�ۂ��o�����X�ǂ��܂܂�Ă���̂ŁA�������𐳏�ɐ����Ă���܂��B
�A�r�^�~��A
�����ɂ͌������Ȃ��r�^�~��A�B
�������⎋�͂̉ɂ����ʂ�����܂��B
�B�r�^�~��B
�����̑�ӂ������Ă���邱�̉h�{�f�B
�_�C�G�b�g�ɂ����Ă���܂����
�C�r�^�~��E
�R�_���͂̍����r�^�~��E�B
�A���`�G�C�W���O�ɕK�v�s���ȉh�{�f�ł��B
�D���J���e��
�̓��Ńr�^�~��A�ɕϊ�����܂��B
�r�^�~��A�̓����Ɠ��l�������⎋�͉A�Ɖu�͂����߂���ʂ�����܂��B
�ȏ�A���ڂ���ɂ͂�������̊������h�{�f���܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
������]�����ƂȂ��H�ׂ�ƁA���h�{�f��ێ悷�邱�Ƃ��ł���̂ŁA����c�����H�ׂĂ��������ˁB
�܂Ƃ�
�ȏォ�ڂ���̐H�߂��ɂ��e���ƓK�ʂɂ��ď������Ă��������܂����B
- ���ڂ���̐H�߂��ɂ�銹��ǂ͎��R��������B
- �_�C�G�b�g�ɕs�����̃C���[�W�̋������ڂ��Ⴞ���A�H�ו�����Ń_�C�G�b�g�̖����ɂȂ�B
- 1���̓K�ʂ�100�`200g�O��B
- �֔����������Ȃǂɂ����ʂ�����B
�Ƃ������Ƃ��킩��܂����I
�Â��Ăق����肵�����ڂ���B
���������H�ׂāA����ɂ���ȂɊ��������ʂ�����ƕ�����A����ɂ��ڂ���̗��ɂȂ�܂��ˁ�
�������o�����X���厖�ł�����A�H�߂��ɂ͋C��t���A���ڂ��ᗿ�����y���݂܂��傤�I
���̋L�������Ȃ��̂����ɗ��Ă�K���ł��B
���킹�ēǂ݂������ڂ���ɂ��Ă̂������ߋL��
�֘A�y�[�W
- �X�[�p�[�Ŕ������J�b�g���ڂ���̕ۑ����@�Əܖ����� �J�r�̌�������
- �X�[�p�[�ł́A���ڂ��Ⴊ������4����1�ɃJ�b�g���ꂽ��ԂŔ����Ă܂��B �ł�����A�ƂɎ����A���Ă��̂܂܂ɂ��Ƃ��Ƃ�������܂��B �X�[�p�[�Ŕ������J�b�g���ڂ���̐������ۑ����@��ܖ�������������܂��B
- ���ڂ�����𓀂�����܂����Ȃ�H �������Ⓚ�Ɖ𓀂̕��@�́H
- ���ڂ����Ⓚ���ĉ𓀂�����܂����Ȃ����I ����͂��ڂ���ɐ����������A�Ⓚ�Ɍ����Ȃ��H�i������ł��B ���ڂ���̐������Ⓚ�𓀂̎d����������܂��B
- ���ڂ���̔�ނ��̃R�c�́H�m���ĊȒP����炸�̂��ڂ���̔�ނ��I
- ���N�H�ނƂ��Ē��ړx���������Ă��邩�ڂ���ł����A��������ς�����A�Ə��ɓI�ɂȂ��Ă��܂��H ���͂��ڂ���̔�ނ��͂ƂĂ��ȒP�ɂł��܂��B ���ڂ���͖Ɖu�͌���A�A���`�G�C�W���O�A�₦���A�ᐸ��J�A�֔�\�h�A�R���X�e���[�������p�A���ɁA����ɂ���\�h�ɂ܂Ō��\������ƌ����Ă��܂��B �܂��ɗ��z�I�ȐH�ނł��邩�ڂ���̔�ނ����ȒP�ɂ�����@������������܂��B
- ���ڂ���͉Ė�������I�~��ɊԈ���邩�ڂ���̂܂ߒm��
- �R�͏t�A�g�}�g�͉āA�L�m�R�͏H�A���ڂ��͓~�ƁA�{�̂킩��₷���H�ו����Ă���܂���ˁB �������A���낢��ȋG�߂ɐH��։^��Ă���̂����ڂ���ł��B ���̌̂ɁA���ڂ���̏{�́H�A�ƕ�����Ȣf���l�������ł��傤�B ���{�̂��ڂ���̏{�͉Ăł��B ����́A�l�G��ʂ��ďo�Ԃ������Ȃ������ڂ���̂܂ߒm����������܂��B
- ���ڂ���͏����̂�����H���ڂ���̌��\�������悭�ێ悵�悤�I
- �h�{���L�x�ŏ������������ڂ���́A�����H��a�l�H�Ƃ��Ă悭���p����Ă��܂��B ���ڂ���͏��������₷���H�ו��Ȃ̂ł��傤���H ����͂��ڂ��Ⴊ�����̂悢����ǂ������ׂĂ݂܂����B ���ڂ���̉h�{�������悭�ێ悷�钲���@�ƃ��V�s�����킹�Ă��Љ�����܂��B
- ���ڂ�����_�炩��������@�I�����W�ŊȒP���Z�I����ł̎菇���Љ�I
- ���ڂ��������Ƃ��A����ł��A��̂Ɏ��Ԃ�������܂���ˁB �ł�����ڂ���͏_�炩�����āA�ȒP�ɒ����ł���ō��ł��B �d�q�����W�̎��Z���@�≺��ł̎菇���܂߁A���ڂ�����_�炩��������@���Љ�܂��B
- ���ڂ���ŐH�ׂ���H���V�s��H�p���ڂ�����Љ�I
- �z�N�z�N�Ǝς��Â����ڂ��Ⴊ��D���ŁA���̂��ڂ���Ȃ�čd���ĐH�ׂ��Ȃ��ł���ˁB �����l���Ă������ł����A�Ȃ�Ɓ@���ŐH�ׂ��邩�ڂ��Ⴊ��������ł��I �����ō���͐��ł��ׂ��邩�ڂ���ɋ��������A�F�X���ׂĂ݂܂����B
- �d�����ڂ�����ȒP�ɐ���@�Ƃ́H�d�q�����W�ŏ_�炩���Ȃ�H
- ���ڂ�����Ă��Ȃ�d���̂Ő�ɂ�����ł���ˁB �ȒP�ɐ���@�͂Ȃ��̂ł��傤���H �d�q�����W�ŏ_�炩���Ȃ�Ƃ����b�������܂����{���Ȃ�ł��傤���H �����W���g���E�g��Ȃ����@�܂߂čd�����ڂ�������@���Љ�܂��B
- ���ڂ���͐��Ȃ��Ɗ댯�I�H���������́H
- �݂Ȃ���͂��ڂ��������܂����H ����́A���ڂ���͐��Ȃ��Ɗ댯���A�܂����������ڂ���̐��ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B