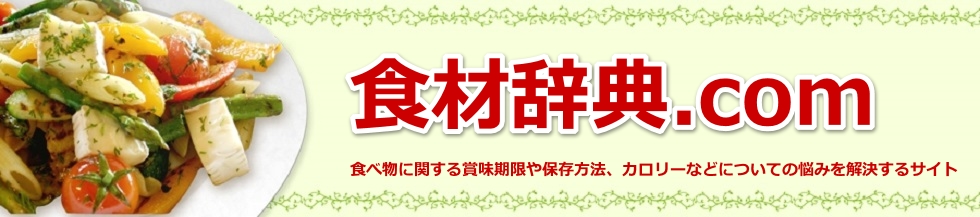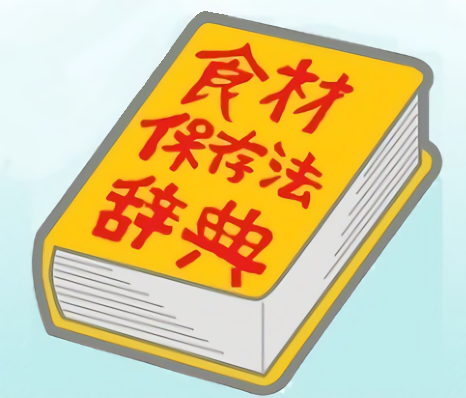きのこは消化しにくい?栄養は摂れるの?便秘解消やダイエットにいい?

きのこが消化しにくい食材であるのは聞いたことありますか?
以前きのこは消化が悪いので、風邪をひいたときは控えた方がよいといわれたことはあります。
ここで気になるのですが、きのこが消化しにくいのなら栄養は摂れるのでしょうか?
またきのこは便秘解消やダイエットに効果的と聞いたこともありますが、本当でしょうか。
きのこは消化しにくい食材なのか、栄養は摂れるのか、便秘解消やダイエットに効果があるのか紹介します。
きのこは消化しにくい食材なの?
まず、きのこは消化しにくい食材なのでしょうか?
ずばり、その通りなんです。
きのこは不溶性の食物繊維を多く含んでおり、消化しにくい特徴を持っています。
またきのこ以外にもごぼうや大豆、穀類なども同様の食物繊維を多く含んでいます。
不溶性食物繊維とは?なぜ消化しにくいの?
その前に、不溶性食物繊維とは何のことかわからないですよね。
実は、食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、水に溶けやすい水溶性と違い、不溶性は水に溶けにくく、その代わりに水分を吸収しやすい特徴を持っています。
水に溶けにくいため消化されにくく、水分を吸収すると数十倍となって便として排出されやすくなります。
つまり不溶性食物繊維を多く含んでいると、消化が悪く、その分水分を吸収して便になりやすいというわけです。
消化に悪いものを食べるのはよくないイメージでしたが、便を出しやすくしていたのですね。
またこの食物繊維を多く含んでいると、食べるときに自然とよく噛むことになります。
このことで食べ過ぎを防ぎ、顎の発育を促すので、歯並びをよくする効果もあるのです。
ちなみに消化しやすいものばかり食べていると、便にはなりにくいですし、消化吸収能力が低くなってしまうと、下痢をすることもあるので注意が必要です。
ただ食物繊維を摂ればよいと思っていたのですが、便を増やすためには消化の悪い食べ物を食べないといけないんですね・・・。
そういった意味ではきのこは消化しにくくても食事に取り入れやすいですし、どの組み合わせにも合うので、よい食材といえますよね。
きのこは消化されなくても栄養は摂れるの?

きのこが消化されにくいことがわかりましたが、それで栄養は摂れるのでしょうか?
実は、栄養を逃さない食べ方が3つあるんです。
1. きのこは水洗いしないで調理する
1つ目は、水洗いをしないでそのまま調理することです。
どんな食材においてもまずは水洗いをしますよね。
ただきのこの場合は、そのほとんどが水洗いをすると栄養が水に流されてしまう可能性があるのです。
その理由ですが、きのこの中に水溶性の栄養が少なからず含まれていることにあります。
水にさらすと栄養が流され、さらに水分を吸ってきのこの食感が落ちてしまい、風味も逃してしまう可能性があるのです。
せっかく食べるのに水洗いをすると逆効果になってしまうわけですね・・・。
それでも気になる方はキッチンペーパーを濡らして表面を拭くか、軽く振り洗い程度にしておくとよいでしょう。
2. 短時間で調理して風味や食感を残す
2つ目は、短時間で調理して、風味や食感を残すことです。
きのこは長時間加熱すると、栄養が損なわれてしまう特徴があります。
油も吸いやすいため、他の食材と一緒に炒めるときは、火の通りにくい食材を先に炒めてからきのこを入れて短時間で加熱するとよいでしょう。
ポイントは、少量の油で、少し炒め足りないかなと思うくらいで加熱することです。
確かにしいたけやしめじなどを長時間加熱したときは、小さくなってあまりおいしくないですよね。
私は順番を気にせず先にきのこを入れることが多かったのですが、次からは後から炒めるようにします。
3. 冷凍して旨味を出しやすくしておく
3つ目は、冷凍して旨味を出しやすくしておくことです。
冷凍保存したきのこを料理として使うときもあるかと思いますが、凍ったまま使う方が旨味や風味、栄養が残ることは知っていましたか?
実は、冷凍したきのこを先に解凍してしまうと、溶けた水分で旨味も溶け出してしまうことがあります。
きのこを冷凍すると中にある水分が膨張し、風味も旨味も溶けだしやすくなるのですが、先に解凍することで、その美味しい部分も一緒に溶け出してしまうのです。
せっかく食べるのですから美味しく食べたいですし、解凍せず凍ったまま調理することをおススメします。
消化の悪さが便秘解消やダイエットに効果がある?
ここできのこの消化の悪さが便秘解消やダイエットに効果があるのか気になるところですよね。
実際に効果は・・・・、あります!
その理由ですが、きのこに含まれる代表的な3つの栄養にあります。
食物繊維が豊富である
まずは、不溶性食物繊維が豊富なことです。
この食物繊維は腸の活性化を促すため、便秘解消や大腸がん予防に効果があり、これ以外にもコレステロールの低下や動脈硬化、高血圧を予防します。
まさに健康食材ですよね。
この腸の活性化ですが、代謝をよくする効果も持っています。
実は腸と代謝機能は密接な関係にあり、腸の機能が低下すると、肝臓に負担がかかり、代謝機能が落ちてしまうのです。
代謝は糖や脂肪をエネルギーに変換させる機能があるため、代謝機能が落ちると痩せにくい体になってしまいます。
つまり、食物繊維を摂って、腸を活性化させることでダイエットへの効果が期待できるのです。
きのこは消化が悪いことでまさに便秘解消やダイエットに効果を持っているのですね。
ミネラルやビタミンDが豊富である
次に、ミネラルやビタミンDが豊富なことが挙げられます。
まずミネラルですが、微量でも骨や体を作り、体の調子を整え、疲労回復効果を持っています。
そしてビタミンDですが、筋肉増強や脂肪予防、カルシウムの吸収、骨粗鬆症の予防に効果を持っています。
つまり、ダイエット向きの栄養素なわけですね。
またビタミンDは脂溶性でもあるので、油と一緒に摂ると、吸収率が高まる特徴を持っています。
きのこを炒めるなどして食べることで、よりミネラルやビタミンDの持つ効果を得られることになるのです。
ただし過剰に摂ると、食欲不振や嘔吐、カルシウム多量による腎機能障害を起こす可能性もあるので注意が必要です。
何事も食べ過ぎないようにしないといけないですね。
まとめ
ここまできのこは消化にしくいのか、栄養は摂れるのか、便秘解消やダイエットに効果があるのかをまとめました。
- きのこは水に溶けにくい不溶性食物繊維を多く含んでいるため、消化しにくい
- 不溶性食物繊維は消化しにくい分、水分を吸収し便を排出しやすくする働きがある
- きのこは水洗いをせず、短時間加熱で、冷凍保存した場合は凍ったまま調理すると旨味も栄養も残る
- きのこの食物繊維は、代謝を上げる効果があり、疲労回復や骨、筋肉増強などダイエットに効果のあるミネラルやビタミンDも含んでいる
ということでした。
きのこが消化に悪いことは知っていましたが、それが便秘解消につながるとは思いませんでした。
また冷凍保存したきのこはそのまま使う方が栄養も残ることも知らなかったので、味が薄くなる気がしていつも冷蔵保存していました。
これを機にきのこを保存するときは冷凍保存に切り替えようと思います!
関連ページ
- きのこのタンパク質含有量は多い?栄養価や健康への効果は?
- 「三大栄養素のひとつタンパク質の含有量は?」 「きのこの栄養価や効能は?」 などきのこの気になる栄養についてまとめてみました。 きのこの栄養素を効率よく取り入れる簡単な方法もご紹介しますので、ご参考にしてくださいね。
- きのこ嫌いを克服する刻み方や子どもにもおすすめのレシピを紹介!
- 子供の好き嫌いで多いのがきのこ類。 できれば食べて欲しいけど、料理に入れてもすぐバレてしまう・・・。 きのこ嫌いを克服するためのコツとレシピを紹介します。
- きのこアレルギーは存在する?原因や症状とは?対処法も紹介!
- 私の知人でシイタケを食べて湿疹がでた人がいました。 その話を聞いて、きのこ好きの私は心配になりました。 なぜなら、健康を意識して、きのこを積極的に食べるようにしているからです。 そこで、今回はきのこアレルギーの原因や症状と対処法についてまとめてみました。
- きのこ類の賞味期限はどれくらい?賞味期限が書いていない理由も紹介!
- どうしてきのこのパッケージには賞味期限が書かれていないのでしょうか? また、どうすれば長持ちするのでしょう? 今回は、そんなきのこ類のパッケージに賞味期限が書かれていない理由や、正しい保存方法などをご紹介したいと思います。
- きのこは生のまま食べると食中毒の危険?!味や香りはどう変わる?
- きのこは生で食べられるのか。 実はきのこを生で食べるような料理がなかなかないことにはしっかりとした理由がありました! 今回はきのこを生で食べるとどのようなことが起きるのか、どうしても生で食べられるものはないのかを紹介させていただきます!
- マッシュルームの傘の裏が黒いけど食べても大丈夫?腐ってるの?
- 傘の裏が黒くなってしまったマッシュルームは、食べることができるのでしょうか? 今回は、そんなマッシュルームの裏が黒くなってしまったものは食べられるのか、腐っていないのかなどについて、ご紹介したいと思います。