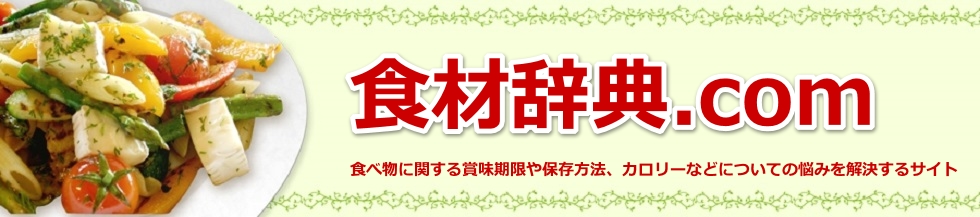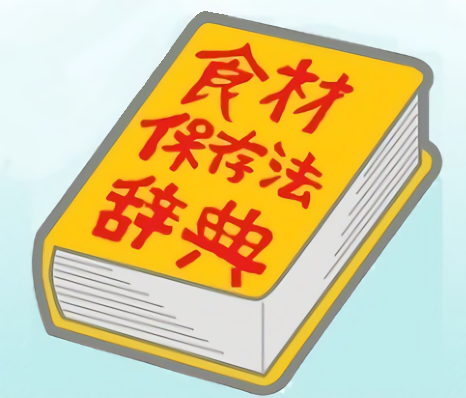とうもろこしを食べ過ぎたら病気になるの?適切な量で期待できる効果は?
とうもろこしって食べ過ぎると病気になる!?
そんな話を聞いたことはありませんか?
嘘のような信じがたい話ですが、どんな病気なのか気になりますよね。
しかし一方で、私はどうもろこしは体にいい野菜!なんて話も聞いたことがあります。
旬のとうもろこしは美味しくてそのまま丸ごとついつい食べてしまいますが、どうせ食べるなら適切な量を食べて、体へのいい効果を期待したいですよね!
今回は、とうもろこしを食べ過ぎたら病気になるのかどうか、また適切な量を食べて期待できる効果についてご紹介していきます。
とうもろこしを食べ過ぎたら病気になるの?
現在は原因解明、そして治療法が見つけられていますが、過去にとうもろこしで「ぺラグラ」という病気を発症させた人たちがいるという記録が残っています。
この「ぺラグラ」という病気が一体どんなものであるのかみていきましょう。
ペラグラの発症
とうもろこし中毒とも呼ばれるこちらの病気は、とうもろこしを食べ過ぎることによって皮膚炎や下痢などの症状を引き起こします。
とうもろこしのたんぱく質の中には必須アミノ酸のひとつであるトリプトファンが少ないことが原因とされています。
おもにとうもろこしを主食とする国の人々の間ではやったようですが、やはり食べ過ぎはよくありません。
気をつけてくださいね!
他にもとうもろこしを食べ過ぎることによって起こりうる体への影響がいくつかあります。
糖質の摂りすぎ
とうもろこしには糖質が多く含まれています。
日本ではご飯が主食ですが、世界的にみればトウモロコシを主食として食べる人たちもおり、世界三大穀物の一つです。
それだけカロリーが高い食べ物といえます。
中くらいのとうもろこしの1本可食部のカロリーは、173カロリーで茶碗一杯分に匹敵します。
とうもろこしと食べるときには主食を少し減らすなどの対策が必要です。
そうでなければ、カロリーオーバーで肥満の原因となるだけでなく血糖値もあげてしまいかねません。
塩分の摂り過ぎ
缶詰タイプのとうもろこしには塩分が多く含まれています。
何も考えずに食べていては塩分の摂りすぎになります。
また茹でる時も塩を使わず湯がくことで、塩分を過剰摂取することなく自然な甘みを感じながら食べることができます。
とうもろこしの1日の適切な量と期待できる効果!
1日の適切な摂取量は約80g〜90gです。
これは中くらいサイズのとうもろこし半分の量にあたります。
ここまでご紹介してきた通り、食べ過ぎには注意したいとうもろこしですが、適量摂取することで次のような効果が期待できますよ!
疲労回復効果
消化が非常によく、エネルギー代謝を促進するトウモロコシには、疲労回復効果があります。
便秘解消
とうもろこしに含まれるセルロースという食物繊維が、善玉菌の餌となり大腸のぜん動運動を促進するため、便秘解消に役立ちます。
また大腸ガンの予防にも効果があるといわれています!
むくみ解消
とうもろこしを食べることによってむくみ解消効果も期待できます。
可食部もそうですが、新しく柔らかい髭の部分であれば、お茶にして飲んだり、天ぷらにして食べると特に効果が得られます。
動脈硬化の防止
とうもろこしに含まれる栄養素はバランスが良く、リノール酸にはコレステロールを下げ、動脈硬化の防止に有効です。
美容効果
ビタミンEやカリウムを多く含むとうもろこしにはアンチエイジング効果があるだけでなく、冷え性にも効果があるといわれています。
適量のとうもろこしを楽しむことで、体への良い効果を積み重ねていきましょう!
とうもろこしを使った料理紹介!
トウモロコシがおいしく簡単に食べれる料理のレシピをご紹介していきます!
コーンポタージュ
材料(3人分)
- とうもろこし・・・2本
- 玉ねぎ・・・半分
- バター・・・5g
- コンソメキューブ・・・1個
- 塩コショウ・・・適量
- 牛乳・・・400ml
- 生クリーム・・・40ml
- 刻みパセリ・・・適量
- クルトン・・・お好みで
作り方
- 熱したお鍋でバターを炒め、玉ねぎも合わせて炒めます。
- 玉ねぎが透き通ってきたら、とうもろこしも入れて炒めます。
- 玉ねぎととうもろこしが浸る程度の水を加え、トウモロコシの芯も入れて沸騰させます。
- 沸騰させたら火を弱め、コンソメを入れて少し煮込みます。
- ハンドブレンダーで粒を潰し滑らかなスープにしていきます。
- 最後に牛乳と生クリーム、塩胡椒で味付けをし、火を止めます。
- お皿に盛って、パセリ、クルトンをかければ完成です!
蒸しコーンのひじきサラダ
材料(4人分)
- トウモロコシ・・・1本
- きゅうり・・・半分
- 人参・・・少々
- ハム・・・2枚
- ひじき・・・50g
- リンゴ酢・・・小さじ2
- 醤油・・・小さじ2
- ごま油・・・小さじ2
- 砂糖小さじ・・・小さじ2
- 白ごま・・・適量
作り方
- とうもろこしは芯から外して、軽く蒸しておきます。
- ひじきは水で戻して、しっかりと水気を切ります。
- 野菜とはむは細長切りにしておきます。
- ボウルに調味料を入れて良く混ぜます。
- そこへひじきと野菜、コーンを入れてしっかり混ぜ合わせ、ゴマもふったら完成です!
まとめ
いかがでしたか?
トウモロコシの食べ過ぎは、ぺラグラを発症させる可能性があるだけでなく、体への悪影響も懸念されます。
しかし一方で、適量摂取することでプラスの便秘解消や美容効果も期待できるとうもろこしです。
私はより栄養素を得るためにも、調理法を工夫しています。
それは、とうもろこしを湯がくのではなくとうもろこしを蒸すようにしていることです。
このことによって栄養分を失うことなく調理でき、仕上がりはふっくらかつ自然な甘みがぎっしりと粒に凝縮されるのでおすすめの調理方法です!
今回ご紹介したレシピを参考にしていただきながら、とうもろこしを食卓に取り入れていっていただければ幸いです。
関連ページ
- ピーマンが変色!赤やオレンジなら栄養たっぷり?茶色は危険?
- あ!ピーマンが赤くなってしまった!! 冷蔵庫からピーマンを取り出したら変色していた!! このピーマンって食べられるのか? 今日はピーマンが変色していくその理由と、何色なら食べてもいいのか栄養価はどうかなど、ピーマンの変色についてご紹介していきます!
- ふきのとうのアク抜きは必要?ふきのとうを使ったおすすめレシピは?
- ふきのとうをとってきたけど、アク抜きって必要なのだろうか? ふきのとうも山菜だから、アク抜きが必要な気もするけど、どうやってするのかあいまいな時ってありますよね。 今回は、そんなふきのとうのアク抜きについて、また定番のレシピからちょっと変わったレシピまでご紹介していきます。
- オクラは変色しても食べられる?変色を防ぐ保存方法は?
- 冷蔵庫で変色しているオクラを見つけて、どうしよう!と思ったことありませんか? 変色を防ぐ保存方法があるのなら知りたいですよね。 今回は、オクラは変色しても食べられるのかどうか、またその変色を防ぐ保存方法、新鮮なオクラの選び方についてご紹介していきます!
- 枝豆を食べ過ぎるとどんな影響がある?1日の適量はどれくらい?
- 枝豆の食べ過ぎって体に良くないのだろうか? 身体にどんな影響があるのだろうか? そんな風に思ったことはありませんか? 今日はそんな枝豆の食べ過ぎによる体への影響や適量、身体への効果について順番にご紹介していきます!
- よもぎの簡単あく抜き方法!重曹ありなしの両パターンを紹介
- よもぎを摘んできたけれどあく抜きの方法が分からない! あく抜きには重曹が必要だって聞いたけど、家に重曹がない! 今日はそんなよもぎの簡単なあく抜き方法と美味しい食べ方についてご紹介していきます!
- ブロッコリースプラウトの効果とは!?がんや花粉症に効くって本当?
- ブロッコリースプラウトとは「ブロッコリーの新芽」という意味で、ブロッコリーの種を発芽させた新芽の状態のことです。 ブロッコリースプラウトには様々な栄養があり、その栄養分の高さからメディアでもたくさん取り上げられています。 そんなブロッコリースプライトの効果について紹介したいと思います。
- ししとうの種はとる?とらない? 種の栄養成分とその効果とは?
- ししとうを調理する時、種どうするの?と悩まれた方も多いのではないでしょうか。 私もはじめはよく悩んでました。 今回は、そんなししとうの種をとる?とらない?の疑問を解決します。 ぜひ参考にしてみてください。
- さやえんどうが大きくなっても美味しく食べられる?保存方法は?
- さやえんどうって大きくなると皮が硬くなっていたり、筋があったり、美味しく食べれることができるのかどうかいまいちわからないですよね。 今回はそんな大きくなってしまったさやえんどうは美味しく食べられるのかどうかについて、その保存方法やまたタネとして保存する方法なども合わせてご紹介していきます!
- つくしってどんな味?美味しく食べられるおすすめのレシピは?
- つくしってどんな味がするのだろう? 今回は、つくしはどんな味がするのか、どうしたら美味しく食べられるのかについて調べてみましたので、ご紹介していきます!
- トマトは腐るとどうなる?カビが生えやすい?賞味期限は?
- トマトが腐ると、どんな状態になるのでしょうか? また、賞味期限や正しい保存方法はどうなのでしょうか? 今回は、そんなトマトが腐るとどうなるかについて、詳しくご紹介したいと思います。
- 豆苗の豆は食べられるの?生でも食べられる?食べ方も紹介!
- 豆苗の豆って食べられるのでしょうか? 豆部分も可食部と考えたら、苗部分だけを料理に使用するより、かなりのボリュームアップになりそうだし、魅力的ではあります。 そこで今回は、豆苗の豆の部分は食べられるのか?ということについて確認していきたいと思います!
- かいわれとスプラウトの違いは何?見た目や味の違いは?栄養価の差は?
- かいわれとスプラウトってどちらもお店で見かけるけど違いは何でしょうか? かいわれとスプラウトの違いについて、見た目や味、そして栄養価の差も含めてご紹介していきたいと思います。
- クレソンはどんな味?栄養価とおすすめの食べ方もご紹介!
- 初めて友人から新鮮なとれたてのクレソンをもらった時、どんな味なのか想像ができず恐る恐る食べたのを今でも覚えています。 味だけでなくクレソンにどんな栄養価があるのかも気になりますよね。 今回はそんなクレソンの味、栄養価、そしておすすめの食べ方についてご紹介していきます!
- しなびた春菊を復活させる方法と春菊のおすすめの食べ方!
- 冷蔵庫に入れておいたはずの春菊が、買って数日後にしなびてしまった経験ってありませんか? しなびてしまっても復活させることができたら料理しやすいし、嬉しいですよね。 今回はそんなしなびた春菊を復活させる方法とおすすめの食べ方についてご紹介していきます!
- 小松菜は下茹でしてアク抜きが必要?下ごしらえの方法は?
- 小松菜は下茹でしてアク抜きが必要なのだろうか? 言われてみれば、下茹でが必要なような気もしないでもないような。 今回はそんな小松菜について、 ・下茹でしてアク抜きが必要なのかどうか ・下ごしらえの方法 ・小松菜を使った簡単レシピ をご紹介していきます。
- 小松菜の苦味の取り方と下処理のコツを紹介!
- 今1歳半の娘の子育て真っ最中なのですが、小松菜は栄養があり子供にも食べさせたい野菜の1つです。 でも小松菜は苦みが苦手で食べれない人も多い野菜です。 そんな小松菜の苦みの取り方や下処理のコツ、また大人も子供も喜んで食べれるような小松菜のレシピをご紹介したいと思います。
- ケールとはどんな野菜?美容や健康に良いって本当?
- 青汁で有名なケールって一体どんな野菜なんだろう。 気になったので ・ケールとはどんな野菜か? ・美容や健康に良いって本当か? ・旬の時期や美味しい食べ方 など調べたことをまとめました。
- スティックセニョールは栄養たっぷり!おすすめの食べ方を紹介!
- スティックセニョール、調べてみると実は栄養満点なんだとか。 上手に調理して、栄養を摂りつつ美味しく食べることができたら嬉しいですよね! 今回はスティックセニョールについて、栄養価、おすすめの食べ方、そしてブロッコリーとの違いについてご紹介していきます。
- さやいんげんは茶色くても食べられる?おすすめの保存方法とは?
- 私も冷蔵庫の中で一部が茶色くなったさやいんげんを見つけたことがあります。 その時は、茶色い部分を切り落として、とりあえず調理して食べたことがありますがあまり美味しくありませんでした。 そんなさやいんげんについて、今回は茶色くても食べられるかどうかやおすすめの保存方法についてご紹介していきます。
- たけのこは腐るとどうなる?生と茹でてからの保存期間は?
- たけのこは腐るとどうなるのか。 あまり腐るイメージはないですが、どうなるのでしょうか? 今回はそんなたけのこについて腐るとどうなるのか、また生と茹でてからの保存期間はどれくらいなのかについてご紹介していきます!
- たらの芽のとげは食べられる?上手な下処理の方法とは?
- 私が初めて祖母と一緒にたらの芽を取りに行ったときは、枝や茎にたくさんのとげが付いていて、食べることができる山菜とは思いませんでした。 今回はそんなたらの芽について、とげは食べることができるのかどうか、上手な下処理方法とはどんなものなのかについてご紹介してきます。
- 枝豆が固いときはどうする?柔らかく茹でる方法は?
- ただ茹でて食べると美味しい枝豆ですが、意外とその茹で加減が難しく、固すぎても柔らかすぎても美味しくないですよね。 今回は、枝豆が固いときはどうするべきか、そして柔らかく茹でる方法についてご紹介していきます。