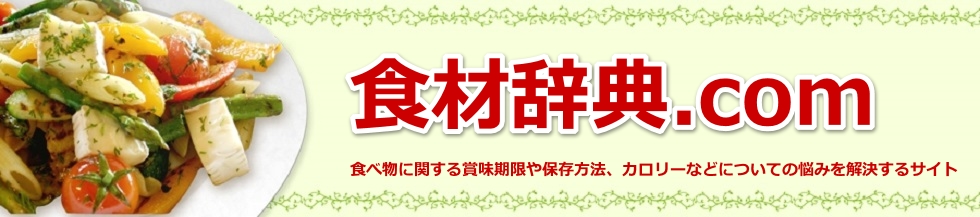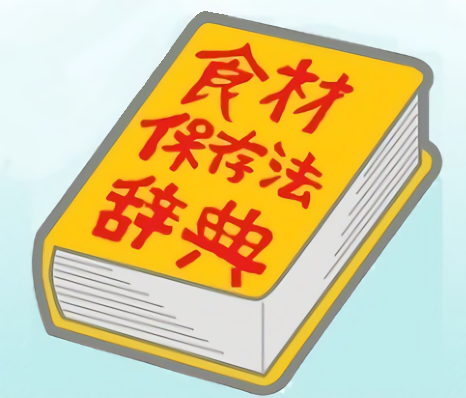�u�J�r�̐������݂͍��ΐH�ׂ��v�͉R�B������x�ƐH�ׂ�Ȃ��Ȃ�B
�����ƌ����Ζ݂ł��ˁB
�����ɖ݂�H�ׂȂ��l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������炢�݂�Ȗ݂�H�ׂ܂��B
����Ȗ݂ł����A���͂��܂�����������A�J�r�������Ă��܂����o���̂���l�͑����Ǝv���܂��B
�ł��̂����݂̓J�r�̕��������ΐH�ׂ���ƐM�����Ă��܂����B
�������A���̍l���͕����ꂽ�̂ł��B
�J�r�̐������݂͋ێ����S�̂ɍL�����Ă����B
�_�ѐ��Y�Ȃ��݂ɐ������J�r�ɂ��Ă�2���̉摜���z�[���y�[�W�ɍڂ��܂����B
���̉摜��������ł��B
�ʐ^1�F���т����������
�ʐ^2 �ʐ^1�̐Ԙg�t�߂����т̋ێ�����������悤�ɐ��F���Č������Ŋώ@�������́i�������̎�������Ɍ�����̂��A���т̋ێ��j
�摜���p���Fhttp://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/mochi.html
�ꌩ�A�܂������J�r�������ĂȂ��悤�Ɍ�����݂̉ӏ����������Ŋg�傷��ƁE�E�E
�J�r�̋ێ����т�����B
���܂��u�J�r�̐������݂͍��ΐH�ׂ��v��M���ĐH�ׂĂ����l�����͎v��������J�r�̋ێ���H�ׂĂ����̂ł��I
�����v���Ƌ��낵���ł��ˁB
���܂ŕ��ʂɐH�ׂĂ��l�̓V���b�N�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����Ă��̉摜�������������x�ƃJ�r�̐������݂͐H�ׂ�Ȃ��Ȃ�����Ȃ����Ǝv���܂��B
���S���Ă��������B�����ł��B
�J�r�͖ڂɌ�����Ƃ��낾���ɐ����Ă�킯����Ȃ��̂ł��B
�J�r�̋ێ��͐A���̍������Ɏ��Ă��܂��B
�A�����h�{���z�����邽�߂ɓy�̒��ɍ�������L���̂Ɠ����悤�ɁA�J�r�͐H�ו��̒��ɋێ���L���āA�S�̂ɒ��菄�点�Ă����̂ł��B
�����Ă��̃J�r�ׂ̍����ێ��͐l�Ԃ̖ڂɂ͌����Ȃ��̂Ŗ݂̂ǂ��܂ŃJ�r���L�����Ă邩�킩��܂���B
���A�摜������ƒ[����[�܂ōL�����Ă�̂��킩��܂��B
�X�|���T�[�����N
�J�r�łŐH���ł͋N���Ȃ��B�ł�����������B
�ł����܂ŃJ�r�̐������H�ׂĂ������������Ƃ͂Ȃ��B
������H�ׂĂ����v���낤�H
�����v������������͂��ł��B
�ł����̍l�����Ԉ���Ă܂��B
���͓��{�Ō��o�����قƂ�ǂ̃J�r�ɋ}�����ł������N�����قǂ̓Ő��͂���܂���B
�܂����ʂ̃J�r��H�ׂ��Ƃ��Ă��قƂ�ǂ̃J�r�͈ݎ_�Ŏ��ł��܂��B
���̂��ߓ��{�ł͉ߋ����\�N�ԃJ�r�ɂ��}���ݒ����Ȃǂ̐H���ł��N��������͂���܂���B
���J�r�ł͂Ȃ��A�������H�i�̒��ő��B�����ۂ�E�C���X�ɂ��H���ł̎���͂�������܂��B
���������ăJ�r���̂͂����܂œŐ��������킯�ł͂Ȃ��A������ƐH�ׂ����炢�ł͉��̏Ǐ���N���Ȃ��̂ł��B
�Ȃ̂ŃJ�r�͈ꌩ���S�Ɍ����܂��B
�ł�������̂ł��B
�J�r�ɂ͔���������A�}���̏Ǐ��N���Ȃ����̂́A�����̏ǏN����̂ł��B
���͕��C�ł������ԏ��ʂł��ێ悵�����邱�Ƃŏ����K���ɂȂ�\���������Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
�K���ȊO�ɂ��A�����M�[��Ɖu�n�̕a�C�ɂ�����₷���Ȃ����肵�܂��B
�݂ɐ�����J�r�̓Ő�
�݂ɐ�����J�r�͐J�r�┒�J�r�ł��ˁB
�����̃J�r�ɓŐ��͂���̂ł��傤���H
�݂ɂ�20��ވȏ�̂����ȃJ�r�������ĂĎ�ނ���肷��͓̂���ƌ����Ă��܂����A��\�I�Ȃ̂͐J�r�ł��B
�J�r
�J�r�͍R�������̃y�j�V������u���[�`�[�Y�ɂ��g���Ă���A�l�Ԃɂ͖��Q�ȃC���[�W�ł��B
���������ׂĂ̐J�r�ɓŐ����Ȃ��킯�ł͂���܂���B
�Ő��̂���J�r������܂��B
�J�r�̒��ɂ̓}�C�R�g�L�V���ƌĂ��A�J�r�ł������̂�����܂��B
�}�C�R�g�L�V���ɂ���ނ�����܂��������u�A�t���g�L�V���v�ƌĂ�镨���͂����Ƃ��댯�ŁA��������������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�݂ɓ����Ă�J�r����ɗL�łƌ������킯�ł͂Ȃ��ł����A�����܂ʼn\���Ƃ��Ĕ����̂���J�r�������Ă�\��������Ƃ������Ƃł��B
������20��ވȏ�̃J�r�������Ă���ƂȂ�Ƃǂ̃J�r���L�ł��킩��܂���B
�ԃJ�r�⍕�J�r���������Ă��肵�Ă��킩��܂���B
�ڂɌ����Ȃ������ł����ȃJ�r�������Ă���݂͊댯�����ƌ��킴��Ȃ��ł��傤�B
���ɔ���������J�r�ł��܂܂�Ă���\���͑傢�ɂ���̂ŐH�ׂȂ��ɉz�������Ƃ͂���܂���B
�͖݂̂ɃJ�r���������炻�̕���������ĐH�ׂ�̂����ʂł�����������͂����H�ׂȂ��̂��펯�ɂȂ�ł��傤�B
�X�|���T�[�����N
�J�r�ł͉��M���Ă����ȂȂ�
�J�r���͉̂��M����Ύ��ɂ܂��B
�ł��J�r�ł͎��ɂ܂���B
�J�r�ł͔��Ɋ�łȂ�ł��B
���Ƃ�100���̂�����1���Ԏς悤��200���̖��ŗg���悤���J�r�ł͐����c���Ă��܂��ƌ����Ă��܂��B
���������ăJ�r�̐����Ă��܂������݂͍���Ă��_���������M���Ă��_���ł��B
�̂Ă܂��傤�B
�̂Ă�ȊO�ɑI�����͂���܂���B
�J�r�������ɂ����݂̕ۑ����@
�ł͖݂ɃJ�r�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ͂ǂ��ۑ���������̂ł��傤���H
�݂͎��͂��Ȃ�J�r�������₷���H�i�ł��B
�Ȃ��݂ɃJ�r�������₷�����ƌ����Ɩ݂ɂ̓J�r�̑�D���ł���
- �^���p�N��
- ����
- ��
��3���L�x�Ɋ܂܂�Ă��邩��ł��B
������H�v���ĕۑ����Ȃ��ƕK���J�r�������܂��B
�ł̓J�r�������Ȃ��ۑ����@�Ƃ͉��Ȃ̂��B
���@�͂���������̂ŏЉ�܂��B
1. �z�b�J�C�����g�����@
- �݂�e��ɓ����
- �e��̂ӂ��̗��ɓ\��^�C�v�̎g���̂ăz�b�J�C����\��
- �①�ɂɓ����
2. �킳�т��g�����@
- �݂�e��ɓ����
- �e��̒[�ɃA���~�J�b�v�ɓ��ꂽ�킳�т�����
- �①�ɂɓ����
�킳�т̑���ɂ��炵�ł����v�ł��B
3. �Ⓚ������@
- �݂�1�����b�v�ŕ��
- �Ⓚ�ɂɓ����
�ǂ�����ɊȒP�ȕ��@�ł��B
1��2�̕��@�͗①��1�`2�T�Ԃ̓J�r���������ɕۑ��ł��܂��B
3�̗Ⓚ������@�͎��Ԃ��o���Ă��J�r�͐����܂���B
���A�Ⓚ�Ă�����̂�3�`4�����ȓ��ɂ͐H�ׂ����������ł��B
�X�|���T�[�����N
���������p�b�N��̖݂Ȃ�J�r�͐����Ȃ�
���͌�̖݂̓J�r�܂���B
���̉Ƃł����N������1�s����̌�̖݂����N�ȏソ���������c���Ă܂����A�܂������J�r��������C�z���炵�܂���B
���̖݂͏ܖ�������1�N���`2�N���炢����܂��B
�������݂��Ȃǂł����݂͂��Ă���1�T�Ԃ���������J�r�������Ă܂��B
���̈Ⴂ�͈�̉��Ȃ�ł��傤���H
���̗��R�͂���������܂��B
- �����ߒ��Ŗ��ۏ�Ԃ�����Ă�
- ����Ȃ����ۂ̏�ԂŃp�b�N�l�߂��A�p�b�N�l�ߌ�����O���E�ۂ��Ă�
- ��̒��ɒE�_�f�ނ����Ă���
���͂��̌�̖݂ɕۑ����̗ނ͎g���Ă��炸�A���ޗ��̕\���́u��������āi�����Y�j�v�Ƃ���������Ă܂���B
�ۑ������g�킸�ɖ݂�1�N�ȏ���������Ă����ȗ��R�̓J�r�̑f�ƂȂ�ۂ���̃p�b�N���ɓ���Ȃ��悤�ɂ��Ă��邱�Ƃł��B
�N���[�����[���łقږ��ۂ̏�ԂŃp�b�N�ɕ���Ă���Ƀ_�������Ŏ��O���E�ۂ��Ă���B
���̌��ʂ��܂ł����Ă��J�r�������Ȃ��̂ł��B
���Ȃ݂ɂ���̓��g���g���тȂǂ������@�Ɠ����������ł��B
�̂͂Ƃ������c�ɂł͍����ł������ʂɖ݂����Ă��̖݂��Ƒ���e�ʂɔz���Ă�����e���ۑ����ĐH�ׂ�ƒ낪���������Ǝv���܂��B
���A�s��̉ƒ�ł͖݂��Ȃ�Ă��Ȃ��̂ōŏ����炱�̌�^�C�v�̖݂��ƒ��������Ȃ��ł��傤���H
�������̌�̖݂��J�r�̐S�z������K�v�͂Ȃ��Ȃ�A�֗��ł���B
������̖݂̌���J�����Ă��̂܂ܒu���Ă����ۂ����ăJ�r�������܂����ǂˁB
�X�|���T�[�����N
�܂Ƃ�
�ȏ�A�J�r�̐������݂͍��ΐH�ׂ��͉̂R���{�����ɂ��ď����Ă��܂����B
�̂͐H�ׂ�̂�������O�ł��������͐H�ׂȂ��̂��펯�ɕς�����܂��B
�펯���Ăǂ�ǂ�ς���Ă����̂ŃC���^�[�l�b�g�ɑa���l�͂��Ă����̂���ς��Ǝv���܂��B
���������̋L����ǂ��Ȃ��͂����J�r�̐������݂�H�ׂ邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�܂��A���������J�r�̐����Ȃ��݂��Ă��܂�����ȔY�݂Ƃ�������ł��B
���N�̐��������N�̐������݂̃J�r�Ƃ͖����ʼn߂����܂���B
�ł͂悢���N���B
�֘A�y�[�W
- �������Ⓚ�ł�����Ēm���Ă��H���������H�ׂ��郌�V�s���Љ�I
- �����A�g����Ă��܂����H���̂܂ɂ��ܖ�������点�Ă��܂�����A�m��Ȃ��ԂɃJ�r�������Ă�����E�E�E�Ȃ�āA���ʂɂ��Ă��܂����Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �ł��A���͂������ȒP�ɗⓀ�ł�����Ēm���Ă��܂����H�Ⓚ�ۑ����ł���A�ܖ��������C�ɂ��邱�ƂȂ�����o���ĕ֗��ł���ˁB ����́A���̂����̗Ⓚ�ۑ��̕��@�ƁA�𓀖@�A�����āA���������H�ׂ���A�����W���V�s���Љ�܂��B
- ������݂͗Ⓚ�ۑ��ł���H�𓀕��@��A�����W���V�s���Љ�I
- ��������������݂��H�ׂ���Ȃ�����ǂ��ɂ��ۑ����������ǁA�Ⓚ�ۑ����Ăł���̂��낤���H ���̂܂܂ɂ��Ă�������ł��Ȃ��Ĉ����Ȃ��Ă��܂����������A���ɕۑ����āA�Ⴄ�Ƃ��ɂ܂�������݂��y���߂���������ł���ˁI ����Ȃ�����݂ɂ��āA����͗Ⓚ�ۑ��ł���̂��ǂ����A���̉𓀕��@�A�����Ď��̌o�����������݂��g�����A�����W���V�s�����Љ�Ă����܂��B