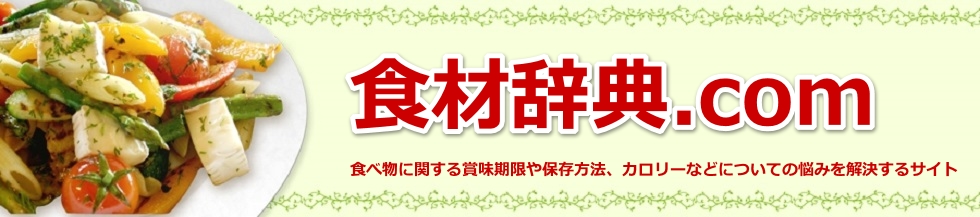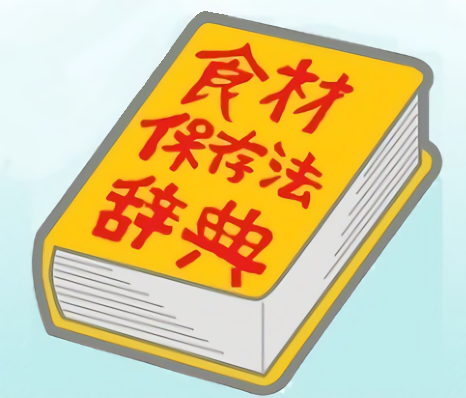カレーが水っぽい原因は?とろみがつくカレーの作り方とは?
子供から大人まで、皆が大好きなカレー。
カレーの香りは食欲をそそりますよね。
でも家でカレーを作ると、水っぽいカレーになってしまった!どうしてとろみがつかないの!
こんなことありませんか?
実はちょっとしたコツで、とろみのあるカレーが作れるようになるんです。
今回、カレーが水っぽい原因と、とろみがつくカレーの作り方を紹介します。
カレーが水っぽい原因とは?
カレーが水っぽくなる原因は、主に材料と作り方にあります。
材料に原因がある
- 水分の多い材料を使った
- とろみを抑える材料を使った
- 煮込むときに水を入れすぎた
カレーに入れる野菜は季節のものや特売品など、そのときによって変えることがありますよね。
でも、季節や収穫した時期で、野菜に含まれる水分量がいつも同じではないので気をつけましょう。
また、魚介類も水分が多い食材となるので、煮込むときの水分量には気をつけたいですね。
一方、カレーに旨味やコクをだすために、隠し味を使うことがあると思います。
この隠し味として、味噌、しょう油、はちみつ、ソース、トマト、野菜ジュース、すりおろしたりんごなどがあります。
ソースやトマト、野菜ジュース、りんごは水分を多く含むので、入れるときは全体の水分量に気をつけてくださいね。
わが家では子供もカレーを食べるので、栄養や消化を考えて野菜ジュースやトマトのホール缶を使ってカレーを作ることがあります。
これだけで結構な水分量になるので、具を煮込むときはその時々で水を加減しています。
ちなみに味噌、しょう油、はちみつを使うと、とろみがつかないことがあるんです。
なぜとろみがつかないかというと、味噌、しょう油、はちみつにはアミラーゼという酵素か含まれていて、アミラーゼはとろみとなるでんぷんを分解してしまいます。
このアミラーゼの働きで水っぽいカレーになってしまうので、注意しましょう。
ところで、カレーに使う食材以外でアミラーゼがカレーに混入することがあります。
それは何のアミラーゼだと思いますか?
答えは、だ液のアミラーゼです。
このだ液がいつ混入するかというと、味見のときに口をつけたおたまやスプーンをそのまま鍋に戻したときです。
ですから、味見をした道具は洗って使いましょう。
私の場合、隠し味にしょう油を使うことがあります。
隠し味は最後に加えると思いがちですが、しょう油のようなアミラーゼを含んだ食材は、煮込んでいるとき入れないとダメなんです。
このアミラーゼは加熱することで働きが弱くなるので、最後の仕上げではなくて具を煮込んでいるときに入れましょう。
そのときは、20分以上煮込むといいですよ。
作り方に原因がある
- 野菜の炒める時間が足りない
- 煮込みが足りない
- 蒸発の少ない鍋を使っている、もしくは蓋をずらさず煮込んでいる
野菜を炒める時間が足りなかったり、煮込みが足りないと水っぽくなってしまいます。
カレーには欠かせない材料のたまねぎ。
このたまねぎにも水分があり、よく炒めると甘味もでてカレーが美味しくなるので、よく炒めて水分をとばしましょう。
意外と気づかないのが鍋の蓋の使い方です。
煮込んでいるとき、鍋の蓋が閉まっていたり蓋のずらしかたが少なかったりすると水分が蒸発しにくいので、水っぽくなってしまいます。
ところで、煮込み料理に使われる圧力鍋や保温調理鍋があります。
カレーは煮込み料理でも、水分を飛ばしてとろみをつけますよね。
圧力鍋や保温調理鍋は蓋がぴったりと閉まった状態で煮込むため、水分が蒸発しにくいのでとろみがつかないんです。
私の場合、カレーの具にスジ肉や骨付き肉を使うことがあり、お肉を柔らかくするために保温調理鍋を使うことがあります。
保温調理後は、やはりとろみが足りないので、蓋を取って煮込んでいます。
このように蓋がぴったりと閉まっている圧力鍋や保温調理鍋は、煮込んだ後に蓋を取って再び煮込んで水分を飛ばすことでとろみがつくんですよ。
カレーが水っぽくなったときに後からとろみをつけられる?
とろっとしたカレーが好きなとろみ派としては、カレーが水っぽいとどうにかしてとろみをつけて食べたい!となりますよね
作ったカレーが水っぽくても、後からとろみをつけることができるんです。
その方法として、
- よく煮込む
- 水で溶いた小麦粉もしくは片栗粉を入れる
- じゃがいもをすって入れる
- とろけるチーズを入れる
があります。
小麦粉や片栗粉、じゃがいも、チーズを入れるときはカレーが固くなってしまうことがあるので、とろみ加減を確認しながら少しずつ入れてください。
特に小麦粉や片栗粉は、ダマにならないように水に溶いたものを入れましょう。
カレールーが入っていて煮込む場合は、鍋に焦げつきやすくなるので、おたまでゆっくりとかき混ぜてください。
私の場合、小麦粉か片栗粉を使ってカレーにとろみをつけています。
このほうが早くとろみがつくので、鍋が焦げつきにくいんですよ。
とろみのつくカレーの作り方
水っぽくない、とろみのつくカレーを作るコツは
- 炒めて野菜の水分をとばす
- 煮込む水の量を加減する
- 隠し味に使う材料の水分に気をつける
- アミラーゼを含む材料を入れるときは20分以上煮込む
- 煮込むときは水分が蒸発するように鍋の蓋をずらす
です。
カレーを作るとき、まずは野菜をしっかり炒めて水分をとばしてください。
そして煮込むときの水は加減して入れすぎないようにしましょう。
野菜ジュースやトマト、すりおろしたりんごを使うときは煮込む水を入れる前に入れて、鍋の水分量を確認してから煮込む水を足すといいですよ。
それから隠し味として味噌、しょう油、はちみつを入れる場合、入れるタイミングが大事です。
これらにはアミラーゼが含まれているので、とろみとなるでんぷんを分解してしまいます。
ですから味噌、しょう油、はちみつは、20分以上煮込むことで酵素の働きが弱まるので、具を煮込むときに入れましょう。
私の場合、カレーに野菜ジュースやトマトのホール缶、隠し味にしょう油を使うことがあります。
水分が加わるのと、しょう油に含まれるアミラーゼの働きで水っぽいカレーになっていました。
そこで加える水を加減して水分量に気をつけ、また、しょう油は具と一緒に煮込むようにしたら、とろみのついたカレーが作れるようになりました。
まとめ
カレーが水っぽい原因と、とろみがつくカレーの作り方について紹介させていただきました。
カレーが水っぽくなる原因をまとめると
- 水分の多い材料を使っている
- 味噌やしょう油、はちみつなど、アミラーゼを含む材料を煮込んでいない
- 煮込む水を入れすぎている
- 野菜を炒める時間が足りない
- 煮込みが足りない
- 蒸発の少ない鍋を使っている、もしくは蓋をずらさず煮込んでいる
です。
とろみがつくカレーの作り方をまとめると、
- 炒めて野菜の水分をとばす
- 煮込む水の量を加減する
- 隠し味に使う材料の水分に気をつける
- 味噌やしょう油、はちみつなど、アミラーゼを含む材料を入れるときは20分以上煮込む
- 煮込んでいるとき水分が蒸発するように鍋の蓋をずらすか取る
私の場合、カレーに野菜ジュースやトマトのホール缶、しょう油を使うことがあります。
煮込む水を加減したり、煮込んで水分を蒸発させて、カレーに使う水分量に気をつけるようにしました。
また、しょう油のようにアミラーゼを含む材料を使うときは、20分以上煮込んだ後にカレールーを入れるようにしました。
こうすることで、水っぽくないとろみのあるカレーが作れるようになりました。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。
関連ページ
- カレーの具を炒めるのはなぜ?炒める時間と順番もおさえよう
- カレーの具材を炒めるのはなぜなんでしょうか? 私も今まで母がそうしているのを子どもの頃からみてきて、自然とそうしていましたが、改めてなぜかと聞かれると明確な答えがわかりませんでした。 そこで今回は、カレーの具を炒めるのはなぜなのかをはじめとして、炒める時間や順番、美味しいカレーを作るコツについてもご紹介していきます。
- カレーは冷蔵保存で何日もつ?常温はNG?日持ちする保存方法のコツ!
- カレーは何日間保存ができるのでしょうか? できるだけ早めに食べてしまうようにしてはいますが、日持ちするような保存方法があれば知りたいですよね。 カレーは冷蔵保存で何日間もつのか、常温保存はできるのか、日持ちする保存方法のコツを紹介します。
- カレーの具材を炒める順番は?美味しいカレーを作るには?
- カレーを作る時って、どの具材から炒めなければならないとか順番ってあるのだろうか?と思ったことはありませんか? 美味しいカレーを作るための順番があるなら是非とも知りたいですよね! 今日はそんなカレーの具材を炒める順番やカレー好きにはたまらない美味しいカレーの作り方をご紹介していきます!
- タッパーについたカレーの汚れが落ちない!きれいに落とす方法は?
- カレーの保存容器といえば、代表的なものがタッパーですよね! しかしカレーを入れてあったタッパーには、くっきりと色移りが… 今回はタッパーについてしまったカレーの汚れや臭い、その落とし方から、汚れがつきにくくなる方法まで紹介したいと思います!