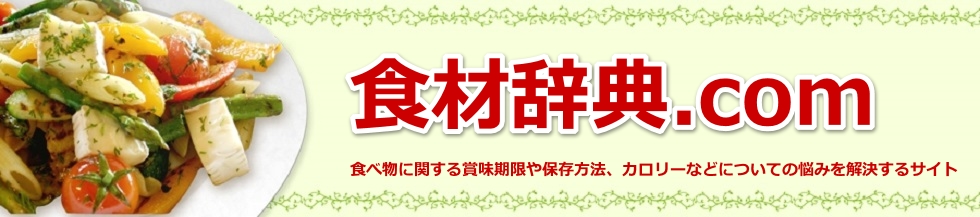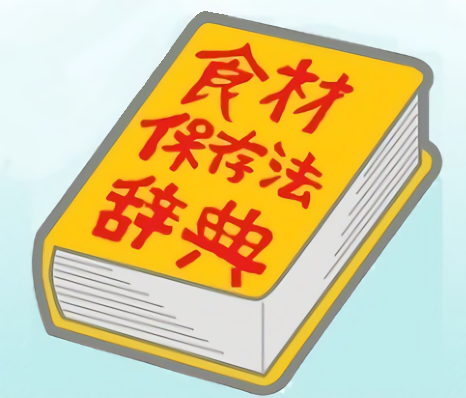びわの種の毒に注意!ビタミンB17と呼ばれていたアミグダリンとは?
平成29年12月5日付で、農林水産省から「びわの種子の粉末は食べないようにしましょう」という注意勧告がだされました。
日本では全国で身近にある果物に対する注意勧告により、注目が集まっています。
健康食材として古来から知られるびわですが、種に毒があるというのです!
もちろん果実は有毒ではありません。
今回は、びわの種に含まれる毒の成分と、健康被害についてまとめてみました。
びわの種に含まれる毒のアミグダリンとは?
アミグダリンは青酸配糖体やシアン配糖体と呼ばれるものの一種で、植物性の自然毒です。
アミグダリンそのものには毒性はありません。
しかし、経口摂取すると、アミグダリンは体内で加水分解されて、青酸であるシアン化水素を発生します。
青酸は猛毒であるため、摂取すると中毒を起こします。
軽度のシアン化合物の中毒症状は
- 嘔吐
- めまい
- 頭痛
- 頻脈
- 呼吸促進
- 代謝性アシドーシス
- 顔面紅潮
などが挙げられます。
重症化してくると以下の症状を起こします。
- 呼吸困難
- 血圧の低下
- 肺水腫
- 心房細動
- 意識がなくなる
- けいれん
- 呼吸停止
- 心拍停止
アミグダリンは、ビタミンだと誤解されていた時期がありました。
ビタミン17と呼ばれ、抗がん作用があると信じられていました。
さまざまな治療法に使用されていましたが、現在、抗がん作用は認められていません。
青酸の致死量は60mgとされています。
びわの種や、その他のバラ科の種子を食べてこの量に達するには、大量の種子が必要です。
1、2個程度の少量であれば死に至ることはありません。
スポンサーリンク
びわの種の飲食による健康被害実態は?
「びわの種」の飲食による健康被害はまだ報告されていません。
では、なぜ農林水産省は「びわの種子の粉末は食べない様にしましょう」という注意勧告を出したのでしょうか。
びわの種のアミグダリンの含有量は2%と報告されています。
果実の中のアミグダリンは、エムルシンという酵素の働きにより、分解され毒素が消えて行きます。
びわの種の核内のアミグダリンは、果実の部分と違い青酸配糖体はほぼ分解せずに残ると言われています。
本来、びわの種のアミグダリンは、砕いたり加熱すると無毒化できます。
しかし、砕かれただけの場合、シアン化水素が糖に分解されるのに時間がかかるため、アミグダリンが残存している可能性があります。
2017年度までに、びわの種を粉末にした食品から有害物質が見つかり回収される事案が4件ありました。
びわの種を単純に乾燥・粉末にした場合、アミグダリンがほとんど分解せずに残っている可能性があります。
回収されたびわの種子粉末食品のうち、有害物資の濃度の高かったものは、小さじ1程の摂取量でも健康に悪影響を与える可能性のあるほどの残有量でした。
びわの種の健康被害は報告されていませんが、他のバラ科の果実による食中毒は時にみられます。
日本では青梅による食中毒被害の報告が、2014年度までの過去50年で患者数は4人います。
そのうち1人は死亡しました。
海外ではアミグダリンによる健康被害の報告があります。
アミグダリン摂取量は一日100mg以内と推奨されていますが、70代の女性が3gを服用し、死亡しました。
アンズや青梅にも含まれている成分ですが、農林水産省はびわの種についての注意喚起をしました。
それは、びわの種子を粉末乾燥した製品が、がんの特効薬、または健康食品であるとうたわれて販売されているためです。
びわの実のアミグダリンは熟すにつれて実のに含まれる酵素により無毒化されます。
また、びわの種を一つ、二つ食べて即健康被害という訳ではありません。
びわの種子は酢漬けや果実酒、杏仁豆腐の香りづけに利用されます。
注意喚起を受けて、現在大手のレシピサイトではびわの種を使ったレシピを削除しました。
スポンサーリンク
大薬王樹 と呼ばれるびわの効能は?
びわは、古来「大薬王樹」と呼ばれています。
びわを植えると病人が集まると言われる程、様々な効能があまる。
民間療薬としても多く利用されてきました。
びわの実は90%が水分のため、のどの渇きを癒す果実として重宝されています。
果実には、カロチン、ビタミンB、りんご酸、カルシウム、クエン酸、鉄分などの成分が含まれています。
漢方でも、口の渇きを癒したり、吐き気を止め、五臓をうるおすとして利用されています。
びわの葉はビタミンB1、サポニン、タンニン、ブドウ糖などが含まれていて、多くの薬効があります。
びわの葉を使った代表的な療法は
- びわ風呂
- 葉焼き:びわ葉の表面を当て、その上から二合ほど温めた焼き塩とコンニャクを布袋に入れて湿布にする。
- びわ茶:夏負けや暑気あたりなどの予防。利尿作用、疲労回復、食欲増進の効果がある。
- びわ葉温圧療法:生のびわ葉の上にもぐさを置いてお灸する。
- 金地院療法:火であぶったびわ葉を皮膚に当てる療法。
- びわ葉の青汁療法:青汁をガーゼに含ませて患部に当てて固定する。切り傷や水虫、たむし、おでき、の殺菌や、あせも、皮膚炎などに有効。
などがあげられます。
びわの花にも咳止めや鼻水止めの薬効があります。
葉も種子も、漢方薬の生薬でもあります。
しかし、生薬として利用されるびわの種子には、原材料に厳格な品質の基準があります。
生薬は医療関係者の管理下で適正に利用されています。
自然毒を含有するびわの種子を、自己判断で選択、利用するのは危険です。
スポンサーリンク
まとめ
びわの種に含まれる自然毒は、バラ科の果実に含まれるアミグダリンです。
びわの種を生食する機会は滅多にありません。
また、びわの実のアミグダリンは成熟すると無毒化するので安全な果物です。
びわは古来からその薬効を認められて利用されて来た植物です。
しかし、種を乾燥したり、アミグダリンを抽出したサプリが販売されるようになったのは最近で、その効果はまだ実証されていません。
びわの種の粉末が含まれるサプリや漢方薬には注意しましょう。
商品のうたい文句を安易に信用して過剰摂取するのは危険です!