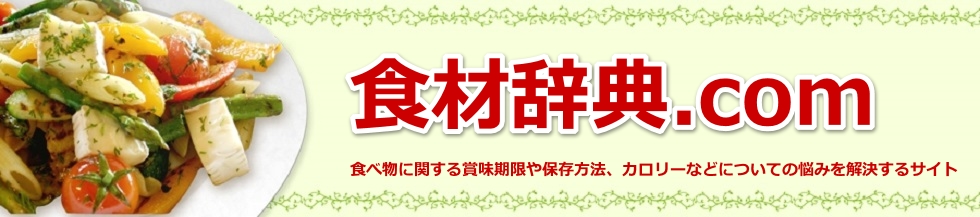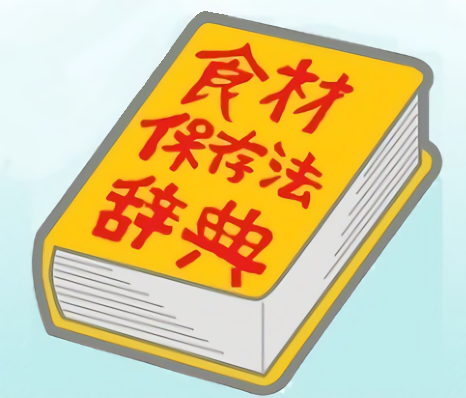ローストビーフは冷たいまま食べるのがいい?温め方と保存方法も!

ローストビーフはどう食べればいいのか迷われる方は少なくありません。
冷たいまま食べるのがいいの?
温めて食べても大丈夫なの?
それらの知識を事前に知っておけば、ローストビーフの美味しさを最大限味わうこともできます。
この記事ではそのようなローストビーフについて、冷たいまま食べてもいいのか、美味しくするためにはどうローストビーフを扱えばいいのかなどについてまとめましたので、ご参考にしていただけたらと思います。
ローストビーフは冷たいまま食べたほうがいいの?

ローストビーフは基本、常温に戻してから食べるようにしましょう。
通常、ローストビーフはスーパーなどでは冷たいまま売られていることが多いですが、冷たいまま食べると、お肉そのものの味や食感がわかりづらくなったりするため、冷たいまま食べるのはおすすめできません。
仮に、常温以上に温めて食べようとレンジでチンした場合には、加熱によるお肉の温度の上昇により、肉汁が出て、それに伴いうま味成分も一緒に抜け出てしまう可能性もあります。
また、レンジで加熱した場合の温度の上昇により、お肉にあるタンパク質が変性を起こし、お肉が硬くなり、食感が損なわれることも考えられます。
ローストビーフは元々低温で焼かれた肉で、中がピンクですが、お肉の柔らかさがおいしさのポイントです。
それを温めることで台無しにしてしまってはもったいないですからね。
また食中毒についてですが、買ってきてから放置する期間が長いと、ボツリヌス菌やサルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(O157)、ウェルシュ菌などの細菌が繁殖してしまう危険性もあります。
これらの細菌が繁殖したものを食べてしまうと、腹痛や発熱、嘔吐や下痢などといった症状にかかるため、買ってきて開封した後は、なるべく早い期間で食べるようにしましょう。
スポンサーリンク
ローストビーフを温めたい場合は?
温めたい場合は、レンジを使う場合は500Wで約30秒程温めると良いとされています。
アルミホイルを使う場合は、ローストビーフをアルミホイルで包んだら、トースターで約15分程温めると良いでしょう。
逆に温めすぎると、お肉がパサパサとした食感となってしまうため、温める時間には注意するようにしましょう。
ローストビーフを美味しく食べるには?

ローストビーフを美味しく食べるにはいくつか方法があり、それぞれ切り方、温度、調理法などを工夫することで可能となります。
まずは切り方ですが、こちらは厚さを約3mm~4mmほどになるように薄く切るのがコツとなります。
薄く切ることによりお肉が柔らかくなり、食べやすくなります。
切る際はお肉の繊維に対して十字になるように切ると、お肉が柔らかくなります。
切る際に用いる包丁ですが、こちらは切れ味が悪い状態のままだと、切る際にお肉が潰れてしまうこともあるため、使う前にしっかり研いでおくようにします。
次は温度ですが、上記でも述べたように常温に戻してから食べるようにすると美味しく食べられます。
常温に戻す時間がない時などは、レンジを使い500Wで約10~15分程温めると良いです。
温めすぎるとお肉がパサパサとなり、食べにくくなってしまうためその点は注意するようにしましょう。
続いて調理法ですが調理法で多いのは、サラダ、丼、サンドイッチにして食べる方が多いようです。
ローストビーフにつけるソースには、ポン酢やワサビ醤油などを使うと、より美味しさが引き立ちます。
また、これらの調理法を用いる際には、盛り付けを工夫するとより一層美味しさを引き立てることが可能です。
スポンサーリンク
ローストビーフを切ると血が出る理由は?
ローストビーフを切ると血のような赤い液体が出ることがありますが、これは血ではなく、ミオグロビンという物質によるものです。
ミオグロビンは筋肉に多く存在しているタンパク質で、ヘモグロビンにより運ばれてきた酸素と結合し、筋肉がエネルギーとして酸素を必要とする時に備えて、酸素を蓄える働きを持ちます。
ヘモグロビンは血液中で酸素と結合し、酸素を運搬する働きを持つタンパク質で、赤血球中に多く含まれています。
このミオグロビンは酸素と触れると鮮やかな赤色に変わるため、ローストビーフを切る際にも、ミオグロビンが酸素と結合してしまうことにより、お肉の中に入っている水分と混じって血のような液体となって出てきてしまうのです。
また、お肉の中に含まれていた血は、販売前にきちんと取り除かれているため、その点は抑えておくようにしましょう。
ローストビーフの保存方法は?
ローストビーフを保存するには、アルミホイルやラップで包み、フリーザバッグなどに入れて冷蔵庫もしくは冷凍庫に保存するようにします。
アルミホイルやラップで包む場合は、中に空気が入らないよう、しっかりとアルミホイルなどとローストビーフを密着させるようにし、フリーザーバッグに入れる際は空気を抜いて真空状態になるようにしましょう。
冷凍庫に入れる場合は、冷凍庫の奥の方に入れるようにすると、冷蔵庫を開けたり閉めたりする時の温度変化による、お肉の劣化を防ぐことができます。
冷蔵庫に入れた場合は保存期間は約3日ほど、冷凍庫に入れた場合は約1ヶ月ほどなので、こうした保存方法を選択する場合は保存期間内に食べるように気をつけましょう。
スポンサーリンク
ローストビーフは本来どのように食べられていたの?
ローストビーフの発祥地はイギリスで、そこでは昔、貴族たちが日曜日に牛一頭丸ごとを使い、「サンデーロースト」としてローストビーフを作り、それを食べていました。
日曜日に食べきれなかったローストビーフの残りは、平日に回すことで、貴族たちの平日の食事としていました。
ローストビーフのイギリスでのオーソドックスな食べ方は、お肉を切る際は薄く切り、お肉を調理する際に出る肉汁を使ったグレービーソースをかけて食べる方法です。
付け合わせには、ヨークシャープディングというシュークリームのようなものをつけます。
このヨークシャープディングは、調理法もそこまで難しいものではないため、オーブンがあれば家庭でも比較的簡単に作れるようです。
イギリスで食べられているようなローストビーフを食してみたい方は、こうした調理法を利用すると、イギリスで料理を楽しんでいるような雰囲気を味わえるかもしれません。
まとめ
ローストビーフは買ってきたら、常温に戻してから食べるようにすると、美味しく食べることができます。
また、その後の調理次第でローストビーフをより美味しく食べることもできますので、余裕があれば調理を工夫してローストビーフを楽しんでみるのも良いでしょう。
ローストビーフがこのように工夫次第で美味しさを引き立たせたり、しっかりとした歴史があるのは筆者もとても驚きでした。
これからローストビーフを食してみようとお考えの方、ローストビーフをうまく調理してよりローストビーフを楽しみたいという方などはこの記事をご参考にしていただけたら幸いです。
合わせて読みたい牛肉についてのおすすめ記事
関連ページ
- 牛肉の中身が赤いまま食べても大丈夫?加熱の仕方や緑色になった場合は!?
- 牛肉をレアやミディアムで焼くと、中身が赤いままの状態となりますが、この状態に不安や疑問をお持ちの方も多いと思われます。 牛肉も豚肉や鶏肉と同様、しっかりと加熱をしないと、食中毒にかかる恐れがあります。 今回は、そのような牛肉について、中身が赤いままの部分を食べても問題はないのか、実際の加熱の仕方や、緑色に変色した場合などについてご説明しましたので、ご参考にしていただけたらと思います。
- 牛肉とガーリックを使用したレシピまとめ!牛肉の焼き加減の目安も!
- 牛肉とガーリックを使用したメニューといえば、ガーリックライスが思い浮かぶ人も少なくないのではないでしょうか。 ですが、他にも、同様の食材を使用したオススメの料理はたくさんあります。 今回は、そのような牛肉とガーリックを使用した料理レシピや、牛肉の焼き加減の種類や確認方法、牛肉を柔らかくする方法などもまとめてみましたので、ぜひ、ご参考にしていただけたらと思います。
- 牛肉はレアで食べても問題はない?焼き加減の種類や確認方法も!
- 牛肉はレアでも食べれるっていうけど、本当に大丈夫なの? 今まで何となく牛肉をレアの状態のまま食べてこられた方も、食中毒に関して正しい知識を持てば、さらにお肉を安心して食べることもできます。 そこで今回の記事では、牛肉をレアの状態のまま食べることの問題性や、牛肉の食中毒の原因菌などまとめてみましたので、ご参考にしていただけたらと思います。
- レンジでステーキが作れる?!簡単牛肉レンジレシピまとめ!
- 牛肉でステーキを作りたいけど、フライパンで調理するのは手間だと感じてしまう場面も多いのではないでしょうか? また、その他の牛肉を使用した様々なレシピについても、フライパンなどで加熱調理を行わなければならず、なかなか手軽に作るのを実現するのに手間取っている方も少なくないのではないかと思います。 そこで今回は、時短レシピとして、レンジで手軽に作れるステーキやビーフストロガノフなどのレシピ、お肉を柔らかくするための一工夫などについてもご説明してみました。
- 牛肉とりんごのレシピを紹介!りんごを使って柔らかくする方法も!
- 牛肉の料理にりんごを使うことで、さらにお料理を良いものへと仕上げることが可能となります。 この記事では、そのような牛肉とりんごを使用したレシピや、りんごを使って柔らかくする方法、食材の組み合わせでカロリーダウン事柄などについてご説明してみました。 ぜひ、ご参考にしていただけたらと思います。
- 牛肉を使った幼児食! 年齢別のオススメレシピを紹介!
- 牛肉を使った幼児食を作りたいけど、どんなお料理を作ればいいのか迷われる方も少なくありません。 ですが、調理の工夫次第で、分量は少なく、大人と同じお料理を提供することも可能となります。 今回は、そのような牛肉を使用した幼児食のレシピや、幼児食の注意点や時期、お肉の焼き加減の確認方法などをご説明して見ましたので、ぜひ、ご参考にしていただけたらと思います。
- 牛肉が臭い!臭みの原因は何?腐っていて食べられない場合の匂いとは?
- 牛肉を買ってきてしばらくすると臭いが気になる…ということありませんか? 食中毒なんかも心配ですよね! そこで今回は牛肉から臭いがした場合に食べられるのか? また独特な臭みを取る方法などをみて行きましょう。
- 牛肉が黒くなった!腐ってるの?食べても大丈夫?
- スーパーで、新鮮そうな牛肉を選び、家に帰って開けてみるとあれ?黒い部分があるー!!なんて経験、あなたはありませんか? この牛肉は腐っているのでしょうか? このまま食べても問題ないのか、牛肉の消費期限と保存方法も合わせて、ご紹介したいと思います。
- 牛肉が茶色に変色する原因は何?緑の場合は?食べられるか見極める方法!
- なんとか半額でゲットした牛肉。 次の日にさっそくお肉を取り出してみると裏側が黒ずんだ茶色の部分がありました。 今回は牛肉が変色する原因と腐ってる?食べられる?の見極め方について調べてまとめてみました!
- 牛肉を牛乳に漬けると柔らかくなって臭みも取れる?牛肉の下処理も紹介!
- 安い牛肉といえば輸入肉で、輸入牛肉は硬いし、臭みもある… どうせ食べるならおいしく食べたい! ちょっとしたコツで、硬くて臭みのあるお肉を、柔らかく臭みのないお肉に変身させることができるんです。 今回、牛肉を柔らかくして臭みも取れる方法を紹介します。
- 牛肉を塩麹に漬けると柔らかくなる?美味しい塩麹ステーキや炒め物レシピ!
- 安い牛肉でも柔らかくなり、さらにおいしさがUPする食材があるんです。 その食材とは 塩? です。 塩?ってどうやって使うの? それはとても簡単で、牛肉に漬けておくだけでいいんです。 今回、塩麹を使って牛肉を柔らかくする方法と、美味しい塩麹ステーキや炒め物レシピを紹介します。
- 外国産牛肉の臭みを取る方法を紹介!臭い原因はなに?
- でも、外国産牛肉って硬いし、臭みもあるし… そう思って外国産牛肉を敬遠していませんか? ちっとしたコツで、臭みのないおいしいお肉に変身させることができるんです。 今回、外国産牛肉の臭みを取る方法、おいしい食べ方を紹介します。
- 牛肉をコーラに漬けると柔らかい高級肉になる!?ステーキや煮込みのレシピ!
- 牛肉を柔らかくするにはお肉専用の叩き器具やお酢、またはお酒を使用して試行錯誤していたのでもっと簡単な方法はないかと悩んでいました。 しかし、実はもっと簡単になんと炭酸飲料のコーラ1つで牛肉が柔らかくなるということを発見しました! ということで今回はコーラで牛肉が柔らかくなるのはなぜなのか紹介するので、是非参考にしてください。
- 牛肉を電子レンジだけで調理できる?何分加熱?臭みが取れないときは?
- フライパンを使用せずに、牛肉を電子レンジだけで調理できたらとても嬉しいですよね。 実は電子レンジのみを使用して牛肉を調理することは可能なのです! というわけでフライパンを使わずに牛肉を調理する方法や注意する点を紹介したいと思います。
- 牛肉を生で食べるのは危険?生食用やレアなら大丈夫?安全な加熱時間は?
- 牛肉は生食でも食べられるのだろうか? 日本国内では実は牛肉は部位によって生で食べることが禁止されています。 なぜ牛肉は生で食べない方が良いのかということを紹介していきたいと思います。