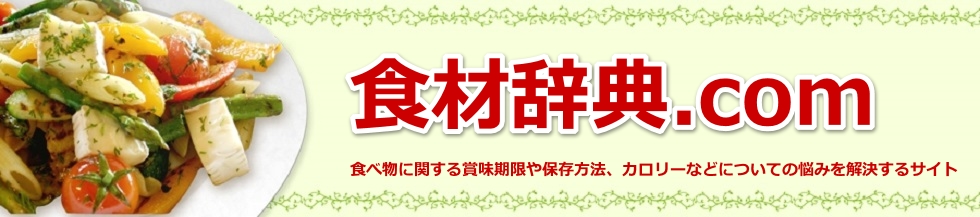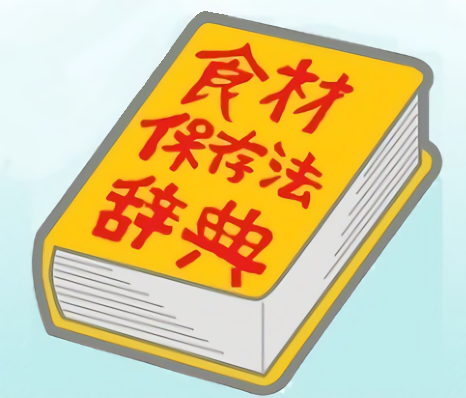無洗米を炊く時の水の量は?美味しく炊くコツ
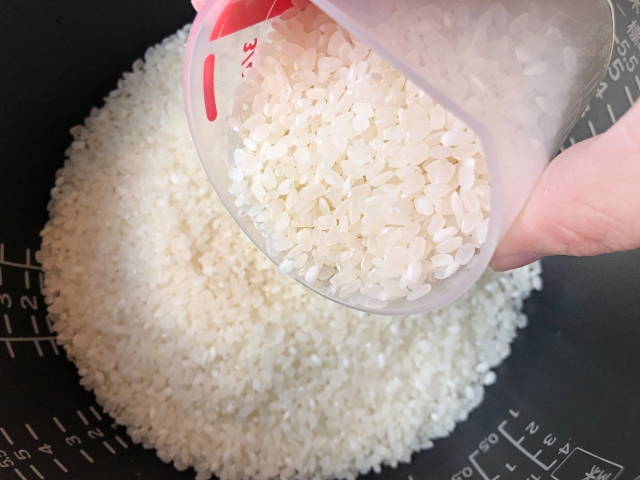
ご飯を炊くとき、無洗米を使ったことありますか?
お米をとがなくてよいですし、ただ水を入れるだけなのでとても楽ですよね。
この無洗米ですが、普通のお米と入れる水の量が違うことは知っていましたか?
私は最近初めて知ったのですが、なぜ入れる量が違うのでしょうか。
無洗米を炊くときの水の量や美味しく炊くコツを紹介します。
無洗米を炊く時の水の量は普通米の時より多め?その理由は?
無洗米を炊くときの水の量はどのくらい入れたらよいと思いますか?
実は、お米の量に対して1.45倍の水の量を入れるんです。
わかりやすくいうと、無洗米1合に対して、炊飯器の目盛り1に水大さじ1〜2杯プラスする必要があるのです。
その理由は、お米のぬかにあります。
無洗米は普通のお米と違って、あらかじめぬかが取り除かれた状態です。
小さくてサラサラしているため、カップに入るお米の量も普通のお米より多くなります。
つまり、普通以上にお米が入る分、水の量もそれに合わせて入れるわけです。
私も無洗米を使ったことありますが、普通のお米と同じように入れていました(汗)。
気持ちお米が固く炊けていたのは、お米の量が多かったからなんですね。
無洗米は本当に洗わなくていい?
無洗米は洗わなくてよいとされていますが、本当に洗わなくてよいのでしょうか?
実は、1〜2回ほど洗った方がよい場合もあるんです。
その判断基準ですが、無洗米に水を入れたときに水が白く濁るかどうかによります。
白く濁る場合は、こげつきや吹きこぼれなどの炊きムラの原因になりやすいとされているのです。
これはでんぷんが白い濁りとなって沈殿した状態であり、この場合は1〜2回ほど洗った方がよいでしょう。
ただし無洗米は洗わなくてよいように加工されているため、洗うときは簡単に水ですすぐ程度にすることが大切です。
洗わなくてよいのが無洗米のメリットですが、洗う場合もあることを忘れないようにしないといけないですね。(汗)。
無洗米をとぐとどうなる?
もし無洗米をといでしまったら、どうなると思いますか?
実は、ベチャベチャになって美味しさも栄養もなくなってしまうんです。
通常、お米は旨味層がぬかで覆われた状態にあり、それを取り除くためにとぐ作業を行います。
しかし無洗米はすでにぬかが取り除かれ、旨味層が表面に出るように加工されているので、とぐ必要がないのです。
また無洗米には水溶性のビタミンB1やナイアシンといった栄養素も含まれており、脂質や糖質の分解、神経症状や皮膚・粘膜の炎症を防ぐ効果を持っています。
つまり、無洗米をといでしまうと旨味層をそのまま取り除き、栄養も同時に洗い流してしまうことになるのです。
これを知らずにといでしまえば、確かにお米は美味しくなくなってしまいますね。
つい習慣で、といでしまいそうですが、無洗米のときはとがないように気をつけましょう。
無洗米を美味しく炊くコツとは?
無洗米を炊く上で、美味しく炊けるコツがあるとうれしいですよね。
実は、そのコツは3つあるんです。
1. 無洗米用の計量カップを使用する

1つ目は、無洗米用の計量カップを使用することです。
無洗米は普通のお米と違い加工されているため、普通の計量カップに入る量は少し多くなります。
普通の計量カップを使用する場合は、1合に対して大さじ1〜2杯多く入れることになりますが、専用カップであれば、ぬかの分だけ少なめに計ることができます。
つまり、水の量を調整する必要がないのです。
なかなか急いでいるときは、水加減を気にしていられないですよね。
無洗米を買う機会があれば、一緒にカップも購入した方がよいかもしれないですね。
2. お米を水にしばらく漬けておく
2つ目は、お米をしばらく水に漬けておくことです。
お米に水を漬けておくことで、お米を吸水しやすくしておくのです。
冬場なら1時間、夏場なら30分ほど漬けておくと、水に溶けだした栄養を吸収した状態でふっくらとお米を炊くことができます。
このときのポイントは、水を入れたら軽くぐるっと混ぜることです。
水を入れると気泡が入り、お米に水が吸収されにくい箇所もあるのですが、軽くまぜることによって全体的に吸収されやすくするのです。
事前にごはんをつくる30分〜1時間前にお米に水を入れておいて、タイミングをみて炊くわけですね。
タイミングをみないといけないのが少々面倒ですが、炊ければふっくらと美味しく仕上がると思うので、試してみてはいかがでしょうか?
3. 炊き上がりは10分ほど蒸らす
3つ目は、炊き上がりは10分ほど蒸らすことです。
これは普通のお米にもいえることですが、炊き上がったばかりのお米は米同士のあいだに水が残っています。
この水もお米に吸収させるために10分ほど蒸らす必要があるのです。
確かに炊き上がったばかりのご飯は水っぽいですよね。
その後、蒸らし終わったら、底から空気を入れるようにお米を混ぜ合わせます。
これにより残った余分な水分を蒸発させ、光沢あるごはんに仕上げるのです。
私は蒸らさずにごはんを食べたことがあるのですが、べちゃっとしていたので、蒸らしは忘れずに行った方がよいですよ。
無洗米のメリットとは?

最後に無洗米を使うとどんなメリットがあるのでしょうか?
そのメリットとは、とぐ手間を省けることです。
無洗米は普通のお米のように2〜3回繰り返しとぐ必要はなく、混ぜるとしてもぐるっと軽く混ぜる程度なので、家事の時間を短縮することができます。
またお米のとぎ汁にはリンや窒素などが含まれているため、水質汚染や排水溝の劣化の原因にもなっています。
しかし無洗米の場合は水を捨てる必要はなく、節水にもつながるので、環境にも家庭にも優しい面を持っています。
とぐ時間が省けることはうれしいことですし、冬場の冷たい水でとぐときは本当に大変ですよね。
価格は少々高いですが、急いでいるときや寒い冬場には最適なお米ともいえますので、使ってみてはいかがでしょうか?
まとめ
ここまで無洗米の水の量や洗わなくてよいのか、美味しく炊くコツをまとめました。
- 無洗米を炊くときの水の量は、ぬかが取り除かれている分、1合に対して水大さじ1〜2杯多く入れる
- 無洗米は白く濁った場合は1〜2回軽く水ですすぐ必要はあるが、基本的に洗う必要がないため、とぐ手間を省くことができる
- 無洗米はすでに旨味層が表面に出ているため、とぐと栄養も美味しさも失われる
- 無洗米を美味しく炊くコツは、無洗米用の計量カップを使用すること、お米を炊く前に水に漬けておくこと、炊き上がりを10分蒸らすことである
ということでした。
私は無洗米を使ったことあるのですが、水の量も事前に水に漬けておくことも知らなかったので、正直いつも固い仕上がりだと思っていました。
普通の白米と同じように水を入れてはいけないことがわかったので、すごく参考になりました。
次回無洗米を買うときは、水の量に気を付けたいと思います!
合わせて読みたいお米についてのおすすめ記事
関連ページ
- おにぎらずの作り方は簡単?作り方のコツや、おすすめ具材も一気に紹介!
- テレビや雑誌でも話題の「おにぎらず」。 見た目にもインパクトがあり、気になっている方も多いのではないでしょうか? おにぎりよりもたくさんのバリエーションがあり、その上、簡単に作れるとなると、ぜひ作ってみたくなりますよね。 今回は、おにぎらずの作り方や、きれいに作るコツ、そして子供から大人まで楽しめるオススメの具材を紹介します。
- 酢飯を冷蔵庫に入れると固くなる!固くならない保存法はある?
- 酢飯を事前に用意しておこうと思うとひっかかるのが、保存方法です。 冷蔵庫に入れておかないと心配だし、かといって冷蔵庫で保存すると、どうしても固くなってしまう… そんな酢飯の上手な保存方法と固くなりにくいポイントを、ご紹介いたします。
- 米を洗わずに炊くと不衛生?米を炊く前に洗う理由は?
- 米を洗うのって面倒なときありませんか? 特に冬は手が冷たくて、洗うのがほんと辛い。 見た目きれいだし、洗わずに炊いても大丈夫なんじゃないの? 今回、米を洗わずに炊くと不衛生かどうか、米を炊く前に洗う理由について紹介します。
- ご飯の芯が残ったまま炊けてしまった時の対処法!リメイクは出来る?
- どうしよう!?ご飯を炊いたら芯が残ってしまった!! 捨てるのはもったいないし、でもこのご飯リメイクできるのだろうか!? もし芯が残ってしまったご飯を上手に対処できたり、リメイクできたら嬉しいですよね! 今回は、ご飯の芯が残ったまま長けてしまった時の対処法とリメイクの仕方、そして美味しいご飯の炊き方についてご紹介していきます。
- おにぎりに塩をつける理由と適量は?つけるタイミングはいつ?
- なぜおにぎりに塩をつけるのか。 それは戦国時代の保存方法のなごりだったんです。 また塩を入れるタイミングはその用途が大事だったんです! 今回は塩おにぎりについて調べました!
- 固くなったおにぎりを柔らかくする方法とリメイクレシピを紹介!
- 固くなってしまったおにぎりを柔らかくする方法はあるのでしょうか? もし柔らかくなれば食べやすいですし、それをリメイクできればまた別の食べ方を楽しめますよね。 固くなったおにぎりを柔らかくする方法やリメイクレシピを紹介します。
- 炊いたご飯が固い時柔らかくする方法!ふっくら炊き上げるコツは?
- 炊き上がったご飯が固かった!どうしよう!? 私はちなみに固く炊けてしまった時、いつもリメイクしてしまうのですが、やっぱり食卓に美味しいご飯が欲しいこともあるので、柔らかくする方法はないのか調べてみました! というわけで、今回は ・炊いたご飯が固い時に柔らかくする方法 ・ふっくら炊き上げるコツ ・固いご飯のアレンジレシピ についてご紹介していきます。