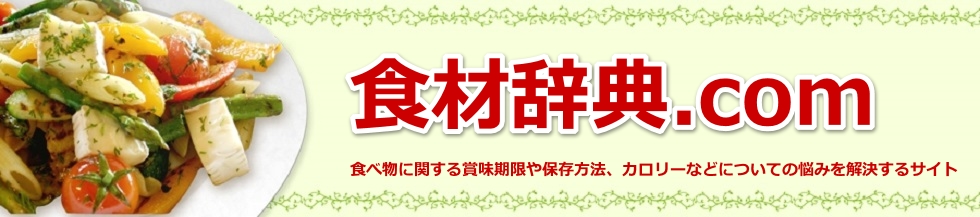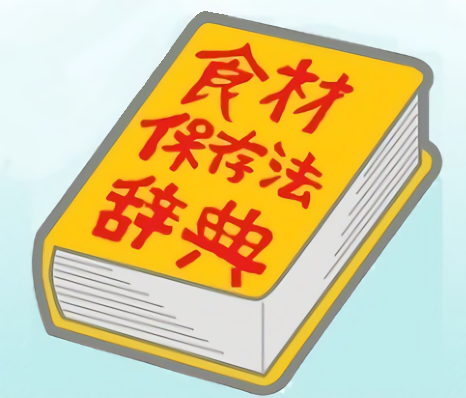りんごの品種のおすすめは? 食べ方別品種の選び方も紹介!

りんご、と一口に言っても色や形によってさまざまな品種があり、その数はなんと2000種類ともいわれています。
普通のスーパーに並んでいるだけでもいくつかの品種があり、どれを選んでいいのか迷ってしまうこともありますよね。
りんごは、品種によってどのような違いがあるのでしょう?
食べ方と合わせて、りんごの品種について掘り下げてみましょう。
りんごの品種、いろいろあるけどおすすめは?
日本で流通量が多く、おすすめされて手軽に手に入る5品種をご紹介します。
1.日本の代表、「ふじ」

ふじは日本で一番生産量が多い品種ですので、耳馴染みもあるかと思います。
ふじは、しっかりとした果肉の歯ざわりと甘味が特徴ですが、甘み・酸味・食感というりんごに求められる3大要素がバランスよく備わっていますので、老若男女から愛されているりんごの代表品種です。
ふじより1か月早く収穫される「早生ふじ」や、収穫が遅くを存分に浴びた「サンふじ」をはじめ、系統の品種も多いのが特徴です。
2.ふじに次ぐ代表格、「つがる」

りんごといえば、の青森県の地名がつけられた、つがるは日本の代表品種です。
食感は、シャクシャクっと歯ごたえのいい「ふじ」に比べると、若干柔らかな口当たりの果実が特徴。
果汁が多めで、噛んだ瞬間にあふれ出る果汁が楽しめる品種です。
10月から流通する他の品種に比べ、9月半ばからと早めに流通し始めるので、りんごの季節の到来を知らせる品種ともいえそうです。
3.青いりんごといえば…「王林」

青りんごといれば「王林」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
その名も「りんごのなかの王様」という願いから名づけられ、ふじ、津軽に次ぐ生産量を誇る品種です。
王林は酸味が少なく甘味が強いのが特徴ですが、後味はさっぱりで、クセがなく食べやすい味と言えます。
やわらかい果肉に反して皮は張っており、噛んだ瞬間、ざっくりと噛みごたえがあるのも特徴です。
4.ニューヨーク生まれの「ジョナゴールド」

ジョナゴールドはもともと日本で生まれたりんごではありませんが、青森県などで多く栽培されています。
ジョナゴールドの特徴は、その見た目。
油が塗られたように赤くツヤ感があり、熟すにすれてさらにツヤツヤ、ロウ質物質が溶け出して表面がベタつくようほどになりますが、それがジョナゴールドの食べ頃サインです。
噛むと、シャキっと固めの食感から、甘味の強い果汁があふれ出します。
5.強い酸味が特徴の「紅玉」

紅玉は見た目はジョナゴールドに似て真紅でツヤツヤ、他のりんごより若干小ぶりなのが特徴です。
甘さを追求して品種改良されるりんごが多いなか、紅玉の最大の特徴は「すっぱい」こと。
果肉は歯ごたえがあって固めで、味は酸味が強く、ひと昔前から変わらぬ味のりんごとして、根強い人気があります。
食べたことのあるりんご、食べてみたいりんごは見つかりましたか?
りんごにもいろいろあることがわかりましたね。
ちなみに私はやっぱり「ふじ」が好きです。
スポンサーリンク
りんごの食べ方別品種の選び方
りんごの食べ方もいろいろあると思います。
丸かじり、料理に使う、スイーツを作るなど。
食べ方によってもりんごの品種の向き・不向きがあります!
そこで食べ方別にりんごの品種の選び方を紹介します。
りんごの一番のシンプルな食べ方は、皮をむいてそのまま食べることですが、りんごは、お菓子や料理など様々なものに加工する食べ方も浸透しています。
生食の際は、とことん好みの食感や味を求めて品種を選べばいいのですが、調理する際は、調理の内容とりんごの品種の相性も考える必要があります。
スイーツ・お菓子向けのりんご
、りんご菓子の代表格であるアップルパイをつく際に圧倒的に支持されるのは、「紅玉」です。
紅玉は、生食だとすっぱいと感じるほどの酸味ですが、砂糖と合わせて煮ることで、それは甘酸っぱさとなってお菓子を引き立てます。
また煮ても煮崩れにくいことで、火を通すりんごのお菓子に最適です。
隠し味向けのりんご
また、カレーのかくし味にりんごを入れるなどという使い方もあるように、料理に使うのに向いているのが「つがる」です。
津軽は果汁が多いので、すりおろすと、その甘くてたっぷりの果汁が料理を引き立ててくれます。
カレーやシチューのかくし味としての他、煮物などに加えると、ほのかな甘味を演出してくれます。
生食に最適なりんご
一方、生食に最適なのが、「ふじ」です。
食感や甘さ・酸っぱさの黄金バランスが、いかにも「りんごを食べている!」という気持ちにさせてくれます。
独特の香りがある「王林」も、調理するよりは生食に向いているでしょう。
酸味が少なく甘みの強い果実は果汁もたっぷりなので、皮をむいて生リンゴジュースなどにするのもおすすめです。
スポンサーリンク
甘くておいしいりんごの品種の選び方とは?
りんごを手軽に味わうなら、やっぱり生でかじるのが一番。
となると、少しでも甘くておいしいりんごの品種や形を見分けて購入したいところですよね。
生食におすすめの「ふじ」の中でも、果実に袋をかけずに直射日光にしっかりあて、収穫時期も若干遅めの「サンふじ」は、特に甘さと酸味のバランスが絶品でおすすめの品種です。
中でも特に、「葉とらずりんご」という記載があるのを見かけたら、それは特に甘いりんごなのでおすすめ!
葉とらずりんごとは?
「葉とらずりんご」はその名の通り、りんごの木の葉をとらずに栽培されたりんごのことで、葉に隠れた部分の果実は色づきが悪いので、一見すると酸っぱそうに見えてしまいます。
しかし、葉で作られた養分が果実に蓄えられて糖になるため、色づきを重視して葉を間引いた一般的なりんごよりも甘味が強い果実が出来上がる、というわけなのです。
またりんごを選ぶ際は、りんごのお尻の部分を観察してみましょう。
りんごの色付きは甘味に直結する要素ではないですが、あまりに緑色のものは未熟ですので、「葉とらずりんご」以外は、お尻までしっかり赤い完熟のものを選びましょう。
お尻の部分が黄色やオレンジがかって透けたような色味になっているものは、蜜が入っている可能性が高いとも言われています。
お尻の形状についても、しっかりと観察を。
とんがったようになっているのは未熟なものが多く、しっかり熟して甘いものは、丸みがかった形状になっています。
スーパーのりんご売り場では、りんごが山積みになって1個単位で売られていることが多いので、りんごのお尻の部分までしっかりとチェックし、より甘くておいしいものを選ぶようにしたいですね。
スポンサーリンク
まとめ
今では1年中、何かしらの品種が店頭に出回っているりんごですが、特にりんごの旬の秋から冬にかけては、さまざまな品種が入れ替わりでお店に並びます。
りんごを食べたときに感じるポイントは、まず歯ざわり。
そして甘さと酸味のバランスや、果肉の柔らかさや果汁の量は、品種によってそれぞれ。
同じような見た目で、いつもなんとなく値段や見た目で選んでいるかもしれませんが、品種を意識して食べ比べてみると、それぞれの差が際立ちます。
そして、せっかく買うからには甘くおいしいものを見極めて、りんごを余すところなく堪能しましょう。
関連ページ
- りんごの芯に白いカビが!?取り除けば食べれるのか?
- りんごの芯に白いカビが生えてる! これって取り除けば食べれるの? カビの正体、食べれるのかどうかを調べてみました。