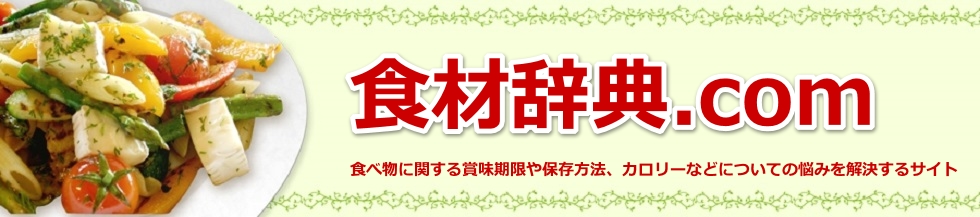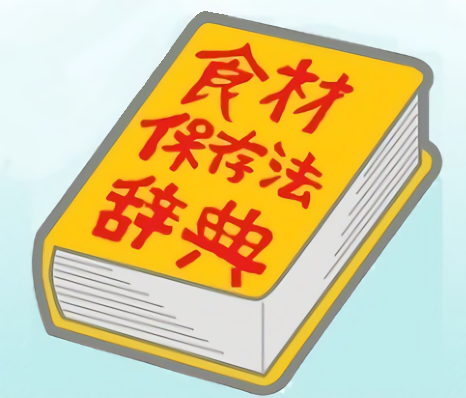干し柿にコバエがたかっても食べられる?コバエを予防するには?
お正月などのために、自宅で干し柿を作るご家庭も多いですよね。
しかし、干し柿を干しているとどこからかコバエがやってきて、干し柿にたかっていたなんてことはないですか?
わたしも自分で干し柿を作ったことはないのですが、一度ご近所で干していた干し柿にコバエがたかっていたのを見かけたことがあります。
コバエのたかった干し柿は何だか不衛生のような気がしますが、食べても大丈夫なのでしょうか?
もしも産卵なんてしていたら…、と考えると、とても気持ち悪いですよね。
今回は、そんなコバエがたかった干し柿が食べられるのか、予防する方法はないのかなどをご紹介したいと思います。
コバエがたかった干し柿は食べられる?産卵してない?
結論から言うと、コバエがたかった干し柿も食べることができます。
というのも、干し柿に寄ってくるコバエはショウジョウバエといって、腐敗したものに接触することがないので、衛生的には問題ないんです。
ショウジョウバエの主な食料は、完熟した果物や樹液などなので、みなさんの思っているほど不衛生というわけではありません。
ショウジョウバエは、アルコールや酢の匂いに引き寄せられてやってきます。
干し柿に使う柿も完熟しているとアルコールのような匂いを漂わせるので、近寄ってきます。
しかし、実際に干し柿を作っていると、柿の中にウジ虫のような虫がわいていた経験があるという方もいます。
これは、おそらく干しているときにたかっていたコバエが柿に産卵し、その卵がかえったことで湧いたのだと考えられます。
コバエの卵を食べてしまっても基本的には胃で消化されてしまうのであまり害はありませんが、食べなくて済むのなら誰だって食べたくはないでしょう。
どうしても不安な方は、コバエのたかった干し柿は避けるようにした方がいいかもしれませんね。
干し柿のコバエ対策は?
干し柿を作るときにコバエが寄らないようにする方法としては、まずはコバエのいない時期に作り始めることです。
コバエは気温が20〜25℃くらいの時に活発に活動するようになりますが、15℃以下になると、活動が鈍くなり、ほとんどいなくなります。
実際に冬になるにつれて、コバエは見かけなくなりますよね。
なので、作り始める時期を遅くして、冬が近づいてから作るようにすることを意識するだけで、干し柿の周りからコバエがいなくなりますよ。
もうひとつは、干し柿を目の細かいネットで覆って干す方法です。
ネットで柿を覆うことで近寄れなくなるので、柿をコバエから守ることができます。
コバエが柿にたかっている姿を見ると、衛生的に問題がないとしてもやはり躊躇してしまいますし、産卵の心配もあります。
柿の周りの糞害も無視できる問題ではないので、やはりできるだけ干し柿を作るときは、対策をしてたからないようにした方がいいでしょう。
美味しい干し柿の作り方
干し柿のコバエ対策が分かったところで、美味しい干し柿の作り方をご紹介します。
必要なもの
- 渋柿
- 紐
作り方
- まず、渋柿の皮を剥く。
- 紐を渋柿のヘタにくくりつけ、重ならないようにいくつかつける。
- 沸騰したお湯に柿を5秒ほどつけ、殺菌する。
- 干し柿を付けた紐を吊るし、干しておく。
この時ヘタと、おしりの皮は残すように注意しましょう。
干し柿の作り方は、たったこれだけです。
皮を剥くときにおしりの皮を残しておくのは、干し柿が自分の実の重さに耐えきれず、形が崩れてしまったり、果汁が垂れて腐るのを防ぐためです。
吊るすときに柿同士が重なってぶつかると、腐りやすくなるので間隔をあけるようにして下さい。
実は干し柿は、乾燥していて風通しのいい場所であれば、室内でも干しておくことができます。
湿度を下げるには除湿器を、風通しを良くするには扇風機などを使うといいでしょう。
干し柿は外で吊るすイメージが強いですが、夜や雨の日は取り込む手間がかかりますし、コバエもたかりやすいので、室内で作ってみてもいいですね。
まとめ
干し柿にたかるコバエは、
- ショウジョウバエといい、衛生的には問題ない
- 産卵する可能性はある
- 気温が15℃以下になると活動が鈍くなり。干し柿にもたからなくなる
- 目の細かいネットで柿を覆うことで、コバエが近づけなくなる
- 干し柿は室内で作ることもできるので、コバエが不安な方にはおすすめ
ということでした。
わたしも手作りの干し柿でも、コバエがたかっているのを見てしまうときっと食べられなくなるので、作るときには時期を見計らわないといけませんね。
衛生的には問題なくても、気分的には大問題なので…。
コバエのたかった干し柿は健康には何の害もありませんが、産卵している可能性もあるので、やはり対策しておくことをおすすめします。
気分よく干し柿を食べるためにも、コバエ対策をしっかりしてコバエから干し柿を守りましょう。
関連ページ
- 柿の実と葉っぱに黒い斑点、食べていいの?黒い斑点の正体とは!
- 柿の実を切ったら黒い斑点がびっしり!見た事がないと驚いてしまいますよね。 実はほとんどの黒い斑点のある柿は問題なく食べられます。 黒い斑点が葉にあっても実にあっても食べられる柿が大半です。 そして黒い斑点の正体は1つではありません。 柿の実と葉に見られる黒い斑点の正体を解説いたします。
- 柔らかくなった柿は食べられる?腐ってる?熟すのを遅らせる方法は?
- 買ってきてから時間が経った柿を食べようと思ったら、いっきに柔らかくなっていた!という経験、ありませんか? 触るだけでムニュっとなってしまうくらいに柔らかくなった柿は、食べられるの?と戸惑ってしまうほど。 熟してるだけ? それとも、もはや腐ってるの? そんな時状態の柿の見分け方や、やわらかくなってしまった柿でもおいしくいただける方法を、ご紹介します。
- 甘くて美味しい柿の品種とは?おすすめの柿ランキング!
- 柿って果物中でもなんというか、ちょうどいい甘さがいいんですよね。 そんな柿にも種類があります。 甘くておいしい柿の品種を調べてランキングを作ってみました。
- 干し柿の白い粉は何?カビとの見分け方と長く保存する方法!
- 干し柿の周りについている白い粉の正体をご存知ですか? 一見カビのようなこの白い粉は、いったい何なのでしょうか? 今回は、そんな干し柿の周りについている白い粉の正体と、カビとの見分け方、干し柿の長持ちのさせ方についてなども一緒に、ご紹介したいと思います。
- 干し柿の白い粉をふかせる方法とカビとの見分け方を紹介!
- 柿に関する悩みや疑問を解決します。
- 柿の皮は食べられる?栄養はある?皮の食べ方や再利用方法!
- 柿の皮は食べられるのだろうか? 皮に栄養があるのかどうかやもし食べれるとしたらどんな食べ方が美味しいのかも気になりますよね。 柿の皮は食べれるのかについて、栄養があるのかどうかも含めて調べてみましたのでご紹介していきます!